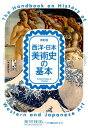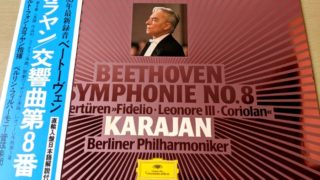美術検定2級合格のための学習を通じて学んだことをご紹介するシリーズ。今回は、第6弾「ギリシアの美術」をお届けします。
とはいえ、まだ「原始・古代の美術」を抜け出せていません。
美術検定の公式テキスト「改訂版 西洋・日本美術史の基本」は、1ページ半強の紙面しか割かれていません。サラッと通り過ぎようと考えたのですが、後世にも大きな影響を与えている「古代ギリシアの美術」。
考えを改めて、ポイントをしっかりと確認することにしました。
この記事でご紹介している画像は、私のセレクト・ミスなどにより本物の画像ではない可能性がありますのでご了承ください。
あらかじめご了承ください。
ギリシアの美術・概要
古代ギリシアの美術の歴史は、BC1000年代の中期から始まっています。「ミケーネ美術」とは地理的に近い範囲だと思いますが、異なる特徴を持っています。
古代ギリシア美術の特徴は、次のような事柄が反映されています。
- 生きている人間が表現されるようになった。
- 理想的な人間の肉体を通じて神を表現した。
- 肉体表現に美と調和を求めた。
ギリシア美術は大きく4つの時代に分類されています。
幾何学様式の時代
幾何学様式の時代は、BC10~BC7世紀の初めくらいまでを範囲としています。
器に描かれた模様には、顕著な特徴があります。
- 対象物の形を単純化させている。
- ①のモチーフに規則性を持たせて配置(組み合わせ)。
この頃に作成されたクーロス(男性の立像)の特徴は、足を並べている状態ではなく、少し前後させることで動きを表現しはじめています。
アルカイック時代
幾何学様式時代の終わり頃~BC5世紀初めくらいまでをアルカイック時代といいます。
アルカイック時代の彫像では、より一層人間の自然な姿が表現されるようになってきます。女性の像には衣類のひだも表現されています。「アルカイック・スマイル」と呼ばれる優しいほほえみが特徴的です。
絵に関してはキャンヴァスに描かれたようなものとは違い、陶器の表面に描かれたもので知ることができます。代表的なものとして、BC540~BC530年頃に作られたエクセキアス作「将棋を指すアキレウスとアイアス」という黒絵式陶器に描かれたものがあります。
建築に関する特徴としては、大理石が用いられた大きな神殿が造られ始めます。
クラシック時代
アルカイック時代以降~BC330年頃までをクラシック時代と呼びます。当時のギリシアは都市国家(ポリス)を形成していました。(そういえば遠い昔、歴史で学んだ記憶があります。)
彫像には、幾何学様式時代のクーロス(男性の立像)よりもさらに動きのあるポージングが見られるようになります。
BC490~BC480年頃に作られた「クリティオスの少年」の立像は、重心が片足に置かれているのがわかります。残念ながら、両肘から指先までの部分と前に出した右ひざ下は残っていません。
絵画のモチーフには、神話や歴史的出来事が使われています。
建築物としては超有名な「パルテノン神殿」が建てられました。
古代ギリシア美術の絶頂期といえるのが「クラシック時代」です。
ヘレニズム時代
ヘレニズム時代はBC323~BC31年までの期間です。
ヘレニズム時代の特徴は、リアルな表現の追求といっても過言ではないでしょう。次の彫刻によの特徴が顕著に現れています。
- ラオコーン(BC40~BC30年頃)
- ミロのヴィーナス(BC190年頃)
- サモトラケのニケ(BC2世紀末)
ギリシアの美術・作品紹介
ここではギリシア美術を代表する建造物と彫像をご紹介します。
美術検定の公式テキストでも太字で強調されていますので、しっかりと確認しておきたいところです。
ギリシアの美術・パルテノン神殿
 nonbirinonkoによるPixabayからの画像:パルテノン神殿
nonbirinonkoによるPixabayからの画像:パルテノン神殿ギリシャの建築は3つの様式に大別されます。
- ドーリア(ドーリス)式
- イオニア式
- コリント式
パルテノン神殿(BC447~BC438年)は建築家であるイクティノスとカリクラテスらによって建てられた、ドーリア式建築の最高峰です。
パルテノン神殿が建設されたのは、古代ギリシアのアクロポリスのひとつアテナイの聖なる丘の上です。アテナイの守護神である女神アテーナー(ギリシア神話)を祀っていました。
大理石を用いた巨大な建築物の割に、建設期間はそれほど長くありません。というよりも非常に短期間だったといえます。
もともと同じ場所にはアテーナーの神殿がありました。しかしペルシア戦争で破壊されていたのです。その意味では、完全に新築の建物とは言えないかもしれません。
その後パルテノン神殿は、1600年代にオスマン帝国に火薬庫として使用されていました。ヴェネツィア共和国との戦いで爆破され、炎上・破損してしまいました。
現在では世界遺産に登録されています。
パルテノン神殿は、美術検定に出題されるかどうかに関係なく、覚えておきたい建築物です。是非とも、実際に観てみたいものです。
ギリシアの美術・ラオコーン
 Waldo MiguezによるPixabayからの画像:ラオコーン
Waldo MiguezによるPixabayからの画像:ラオコーン作者についてはわかりませんが、大理石で作られたラオコーンは現在、バチカン美術館に所蔵されています。
ラオコーンはトロイア(イーリオス)の神官でした。トロイアといえば、「トロイの木馬」で有名ですよね。
ラオコーンはトロイの木馬がギリシア軍の仕業によるものだと見抜き暴こうとしたのですが、女神アテーナーが送り込んだ海蛇に襲われて殺されたとされています。
ラオコーンと息子二人が海蛇に巻き付かれている場面を描写したのがラオコーン像です。
動きを伴った一場面を切り取ったような迫力のある作品ですよね。
ラオコーンは、後世のミケランジェロにも影響を与えたと言われています。
ギリシアの美術・ミロのヴィーナス
大理石で作られ、203cmもあるミロのヴィーナス。現在は、パリのルーヴル美術館で観ることができます。
ミロのヴィーナスは1820年(文政3年)にエーゲ海のミロス島で発見されました。
題材となったのは、ギリシア神話の女神アプロディーテーだと言われているようです。
両腕がないのが残念ですが、自然と頭の中で想像力が働き始める感覚を覚えます。不思議な作品ですよね。
ギリシアの美術・サモトラケのニケ
 Ciprian AxinteによるPixabayからの画像:サモトラケのニケ
Ciprian AxinteによるPixabayからの画像:サモトラケのニケサモトラケのニケは、勝利の女神ニケが船の舳先に降り立った場面を表しています。
1863年(文久3年)にエーゲ海のサモトラケ島で発見されました。ミロのヴィーナスと同じく、ルーヴル美術館が所蔵しています。
大理石で作られていて、244cmもある大きな彫像です。
両腕だけでなく頭部もない彫像ですが、ミロのヴィーナス以上に想像力を刺激する作品です。正面から風を受けている様子がリアルに表現されています。
サモトラケのニケは、ヘレニズム彫刻における最高傑作と呼ばれるにふさわしい彫像です。もしかすると、完璧な姿で残っていないところが魅力度をアップさせているのかもしれませんね。
ミロのヴィーナスやサモトラケのニケをはじめ、世界的に有名な作品を数多く所蔵しているんだから。
まとめ
- 美術検定対策:ギリシア美術の建築ではパルテノン神殿は外せない!
- ラオコーン、ミロのヴィーナス、サモトラケのニケは覚えましょう!
■参考文献
- 「改訂版 西洋美術の歴史」監修 横山勝彦、半田滋男/編集 美術検定実行委員会/発行 美術出版社
- 「西洋美術の歴史」著者 H・W・ジャンソン、アンソニー・F・ジャンソン/訳者 木村重信、藤田治彦/発行 創元社
■関連書籍のご案内です。
↓