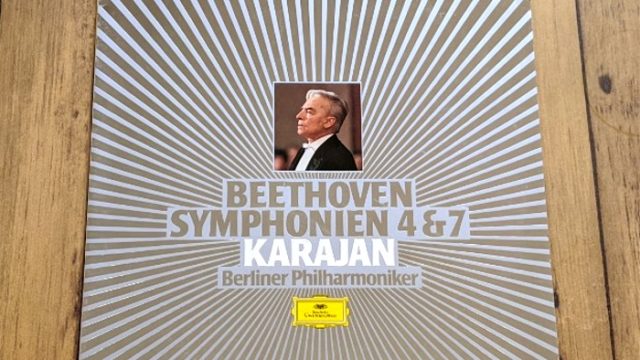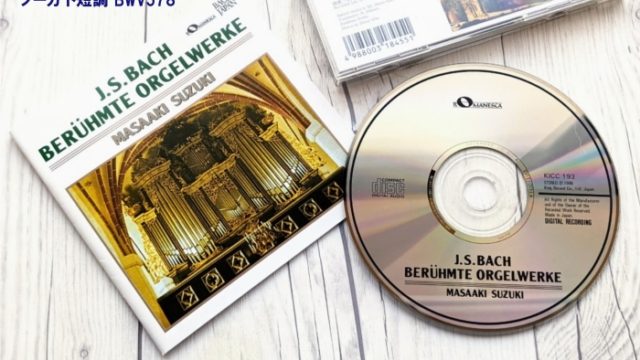イエス・キリストの誕生を祝うクリスマスの時期。
クリスマス・ソングの大定番と言えば、「きよしこの夜」でしょう。
レオンティン・プライス(ソプラノ)の歌声で美しい作品の世界に浸ることに。
指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン、ウィーン楽友協会合唱団のコーラス、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で楽しみました。
■カラヤン/アヴェ・マリア
- ソプラノ:レオンティン・プライス
- コーラス:ウィーン楽友協会合唱団
(合唱指揮:ラインホルト・シュミット) - 演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン
- DECCA【UCCD-9510】
- 発売・販売元:ユニバーサル ミュージック株式会社
きよしこの夜(グルーバー作曲/メイヤー編曲)とは
 イエス・キリストの誕生【オブジェ】
イエス・キリストの誕生【オブジェ】「きよしこの夜」は、最もポピュラーなクリスマス・キャロルのひとつです。
作詞したのはヨーゼフ・モール(1792年~1849年)で、原詞はドイツ語です。
ヨーゼフ・モールの詞に曲を付けたのは、小学校の教師であり、教会のオルガン奏者でもあったフランツ・グルーバー(1787年~1863年)です。1818年(文化15年・文政元年)に作曲しました。
「きよしこの夜」の初演は、1818年(文化15年・文政元年)12月25日のこと。場所は、オーストリア・オーベルンドルフの聖ニコラウス教会です。
「きよしこの夜」が作曲された経緯(いきさつ)には有名なエピソードがあります。
1818年、クリスマスに開催されるミサの直前。教会のオルガンが故障するというハプニングが...
(故障の原因は諸説あるようですが、ネズミにかじられたためというのが一般的です。)
そのためヨーゼフ・モールが急いで詞を書き、フランツ・グルーバーがギター伴奏による曲を付けることに。フランツ・グルーバーは、ギター伴奏の曲は教会では好まれないと思っていたとか...
かくして「きよしこの夜」は、ギターによる伴奏で初演されたのでした。
このエピソードについては、多少の脚色があるようです。
- オルガンの故障原因が本当にネズミによるものだったのか?
- オルガンの故障は、もっと以前にわかっていたのではないか?
etc...
いずれにしても「きよしこの夜」は、タイトル(英語:Silent night)をイメージさせる静かで清らかな名曲です。
「クリスマス」という言葉は「キリストのミサ」の意味なんだよ。
クリスマスはイエス様が誕生した日のことではなくて、誕生をお祝いする日なんだ。
わたなびはじめの感想:きよしこの夜(グルーバー作曲/メイヤー編曲)について
 ウィーン楽友協会
ウィーン楽友協会ここからは『カラヤン/アヴェ・マリア』に収録されている、グルーバー作曲/メイヤー編曲「きよしこの夜」の感想をお伝えします。
※【 】は、今回聴いたCDでの演奏時間です。
■きよしこの夜【3分43秒】
このCDはギターによる伴奏ではありません。
英語の歌詞で歌われる「きよしこの夜」。
レオンティン・プライス(ソプラノ)の歌声は、透明感があり、高く突き抜けていくようで印象的です。「突き抜ける」といっても決して荒っぽくはなく、歌声の端々からやわらかさを感じます。
個人的にレオンティン・プライスの歌声には、清廉さが際立っていて、少し冷たい印象も受けました。この印象には音響が関係しているかもしれません。
実際のところはわかりませんが、冷え切った石造りのドームの中で歌っているような感じとでも言ったらいいのでしょうか。あくまでも私の個人的な感想です。
澄んだソプラノのやさしい歌声で、厳かな気持ちにさせてくれる「きよしこの夜」だと思います。
今回ご紹介している「きよしこの夜」は、カラヤンがウィーン・フィルハーモニー管弦楽団とウィーン楽友協会合唱団(合唱指揮:ラインホルト・シュミット)と共にソプラノ歌手レオンティン・プライスを支えている、すばらしいクリスマス・キャロルになっています。
私はクリスマス・キャロルが大好きなので、今月あと何回聴くことになるかわかりません。
イエス・キリストの誕生を祝うこの時期、やさしい気持ちで過ごしたいところです。
まとめ
- 「きよしこの夜」の誕生エピソードでは、教会のオルガン故障がキッカケと言われている。
- 「きよしこの夜」の初演は、ギター伴奏で行なわれた。
- もっとも有名なクリスマス・キャロルのひとつ。
 |
価格:1,255円 |
![]()