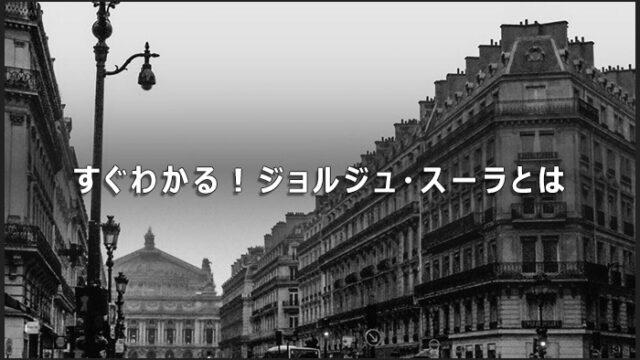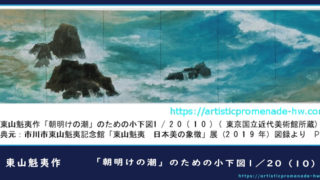日本で最も有名な日本画家の一人である東山魁夷(敬称略)。
東山魁夷の印象を特徴づける作品には、「道」「朝明けの潮(あさあけのうしお)」「緑響く」「山雲」「濤声(とうせい)」「揚州薫風(ようしゅうくんぷう)」等々があります。
日本画家でありながら西洋絵画の技法を取り入れた作品や水墨画など、幅広い許容力を持ちながらも、絵の道を究めるが如く歩んだ人生には、東山魁夷を取り巻く環境や関わった人々の影響が少なくなかったはずです。
私のイメージする東山魁夷は、温和で優しい人柄の持ち主です。
この記事では、東山魁夷の歩んだ道と関わった人達や出来事をご紹介したいと思います。
東山魁夷 日本を代表する日本画家の歴史
 神奈川県・横浜市
神奈川県・横浜市東山魁夷は1908年(明治41年)に横浜市海岸通りで誕生しました。本名は「新吉」さんです。
3歳の頃に神戸に引っ越して青年期までを過ごします。
どちらも港町で海外の影響を受けたエキゾチックな都市だから、ちょっとうらやましいぞ。
でも…明治から大正時代にかけての雰囲気はどうだったのかな?
1914年(大正3年)、6歳のときに第一次世界大戦がはじまります。
中学生時代の東山魁夷
1921年(大正10年)、13歳のときに兵庫県立第二神戸中学校(現在の兵庫高校)に入学します。三年生のときには1学期の途中から夏休みが終わるまで、登校しない期間があったようです。詳しい理由はわかりませんが、人間関係に敏感だったようです。
学校には東山魁夷に関心を持ってくれる先生がいらしたようで、東山魁夷の絵を褒めてくれたり、展覧会にも連れて行ってくれたそうです。
青年・東山魁夷にとって、画家になりたい気持ちを高めてくれた存在だったんだろうなぁ。
画家になることについて東山魁夷のお父さんは、当初反対の意を表したとのこと。先ほど登場した先生とは別の担任の先生の協力を得て、お父さんを説得します。お父さんは「日本画」という条件付きで、東京美術学校の受験を許可しました。
日本画家への道は、このようにして形づくられていったのですね。
東京美術学校で学んだ東山魁夷
1926年(大正15年・昭和元年)に東山魁夷は東京美術学校日本画科に入学します。そこで松岡英丘(まつおかえいきゅう)と結城素明(ゆうきそめい)に指導を受けます。
この当時の日本画はひとつの変革期にあったのです。それまで線描が主体だった日本画に、西洋絵画の影響で「塗る」という手法が加わりはじめていたのです。
東山魁夷に大きな影響を与えたことは容易に想像ができます。
東京美術学校を卒業し東山魁夷になる
1931年(昭和6年)、東京美術学校日本画科を卒業後、東京美術学校研究科に入ります。そして「魁夷」を雅号とします。日本画家・東山魁夷が誕生した瞬間です。
ドイツ留学する東山魁夷
1933年(昭和8年)、東山魁夷25歳で東京美術学校研究科を卒業しドイツに渡ります。
ベルリン大学に留学し、西洋美術史だけでなく日本美術史をを学びます。ヨーロッパを巡る旅もしたようで、西洋の街並みや文化を体感し、西洋絵画も鑑賞することで、自身の画家としての表現について探求したと思われます。
ベルリン大学では積極的な人柄を見せていたようで、頼れる存在だったとか。
1933年のドイツといえば、ヒトラー内閣が成立した年です。
日本はといえば国際連盟を脱退し、情勢は不安定な方向に向かっていた時代でもありました。
東山魁夷はヨーロッパを旅した際に、強く刺激を受けた作品に出合いました。それはサンマルコ聖堂にあるフラ・アンジェリコのフレスコ画「受胎告知」だったそうです。
しかし1935年(昭和10年)、お父さんの病気の知らせを受けて留学を断念し帰国します。
日本に帰国後の東山魁夷
1939年(昭和14年)には、第二次世界大戦が勃発します。翌1940年に結婚するも、1945年(昭和20年)に戦争に召集されて熊本へ行くことに。
無事に生還したのですが、お母さんと弟を亡くします。お父さんは1942年(昭和17年)にすでに他界されていました。
終戦後、画家として筆を執りはじめた東山魁夷でしたが、1946年(昭和21年)に開催された第1回日本美術展覧会(日展)に出品したものの「落選」してしまいます。
戦争、肉親の死、日展での落選など、自暴自棄になってもおかしくなかったかもね。
ドイツで意気揚々としていたころのことが脳裏をかすめたんじゃないかな。
東山魁夷の転機となった「残照」
1946年(昭和21年)、東山魁夷は千葉の鹿野山に登り、九十九谷に沈む夕日を見ていたときです。自然との一体感により、風景に対する意識が変化したようです。その体験に基づいて描かれたのが「残照」でした。
1947年(昭和22年)に第3回日展に出品された「残照」は、「特選」を受賞します。39歳で画壇に迎えられることになりました。
東山魁夷の代表作のひとつ「道」と市川市
1950年(昭和25年)、第6回日展で「道」を出品します。
淡い緑の間の急な斜面に続く一筋の道。この作品で東山魁夷は注目を集め人気画家となります。
試作とはいえ、静寂な雰囲気を漂わせているすてきな作品だったな。
少し薄暗さを感じる空に対して、明るい緑色の草原と三角形のように収束していく白っぽい道が作品全体を暗くさせずにバランスを保っている作品だった。
市川市の話になったので、関連した情報をご紹介します。
1953年(昭和53年)に、東山魁夷は吉村順三氏の設計による家を建てます。それが千葉県市川市中山です。市川市東山魁夷記念館はその隣に建っています。ちなみに吉村順三氏は、東京美術学校時代の同期です。
東山魁夷夫妻、北欧の旅へ
1962年(昭和37年)、54歳の東山魁夷は奥様と北欧の旅に出ます。3ヶ月半ほど北欧に滞在したようです。
「朝明けの潮」の完成
 皇居・二重橋
皇居・二重橋1968年(昭和43年)、皇居新宮殿の壁画を完成させます。それが「朝明けの潮」です。
皇居新宮殿に飾られているのは、幅15メートル、高さ5メートルの大壁画です。緑青、群青等で描かれている波は見事で、波模様も実にすばらしいです。着手から2年半かけて完成したという意味でも大作と呼ぶにふさわしい作品です。
図録に掲載されていた写真を観ての感想だよ。
この時期には「朝明けの潮」の取材旅行の合間を使って、「京洛四季」の制作も進めていたようです。
東山魁夷、ドイツ・オーストリアの旅へ
1969年(昭和44年)に、東山魁夷夫妻はドイツ・オーストリアを旅しています。オーストリアといえば音楽の街でもあります。
オーストリアのザルツブルクといえば、あのモーツァルトの故郷でもありますよね。東山魁夷はモーツァルトのピアノ協奏曲イ長調(K488)第二楽章がお好きだったそうです。白馬のイメージが浮かんだのも、この曲を聴いたときだとか…
東山魁夷、といえば「緑響く」の白馬
東山魁夷も用いたモチーフといえば、「白馬」を連想するかもしれません。
1972年(昭和47年)に東山魁夷は、連作「白い馬の見える風景」を発表します。
緑の森とそれを移す湖面、中央よりやや右側に左を向く白馬を描いた「緑響く」もその1作です。
東山魁夷と「唐招提寺御影堂障壁画」について
鑑真和上像が建立した奈良の唐招提寺。
東山魁夷は、1973年(昭和48年)から唐招提寺の障壁画作成に入ります。中国を旅したり、水墨画を研究し、大作の制作に臨みます。
1975年(昭和50年)に唐招提寺御影堂の第一期障壁画「山雲」「濤声」が完成します。
1980年(昭和53年)に唐招提寺御影堂の第二期障壁画「黄山暁雲」「揚州薫風」「桂林月宵」を完成し奉納します。
襖に描かれた「濤声」で表現されている波の青が鮮やかで美しくて、そそり立つ岩肌の存在感が重厚で息をのむほどの印象を受けたのを覚えている。
唐招提寺の障壁画は、毎年、開山忌にあたる6月5~7日に一般にも公開されているみたいだよ。
東山魁夷の人柄
東山魁夷は、自分の作品から複製画やリトグラフを作ることを許していたそうです。その利益はユネスコ芸術賞の創設、ボストン美術館の日本絵画修復基金の設立に役立てられたとのこと。
阪神淡路大震災の折には義援金を送るなど、お金を人や文化的活動のために使われた方です。そういった姿勢は東山魁夷の人間性を感じる上でも参考になります。
1999年(平成11年)に亡くなるまで、明治から平成の4つの時代を生き抜いた日本を代表する日本画家です。
東山魁夷の交友関係
 旧天城トンネル
旧天城トンネル東山魁夷は川端康成氏と親交があったようです。キッカケは、川端康成氏の古美術コレクションを見せてもらったこととか。
他にも、吉川英治氏とも親交があったようです。
文豪との親交があるというのは、芸術家にとってよくあることなのかどうかはわかりませんが、興味深いですね。表現方法は違えど、芸術・文化の道を歩むという共通点はありますよね。
そういえば、東京美術学校時代の同窓だった吉村順三氏が設計した千葉県市川市の自宅は、アトリエを備えているだけでなく、音楽も楽しむことができたそうです。おそらく、モーツァルトを聴かれていたのでしょう。
東山魁夷作品を収蔵している美術館
 長野県信濃美術館 東山魁夷館
長野県信濃美術館 東山魁夷館ここからは東山魁夷の作品を収蔵している美術館をご紹介します。市川市東山魁夷記念館についてはここでは割愛しますね。
なお、常に展示されているかどうかはわかりませんので、公式サイト等でご確認ください。
東山魁夷作品を収蔵している美術館【東京編】
東京都台東区上野公園12-8
⇒「南天」収蔵。
東京都千代田区北の丸公園3-1
⇒「道」「残照」、「朝明けの潮」のスケッチ・下図など収蔵。
東京都江東区三好4-1-1
⇒「彩林」「森のささやき」収蔵。
東京都千代田区三番町2 三番町KSビル
⇒「年暮る」収蔵。
東山魁夷作品を収蔵している美術館【長野編】
長野県長野市箱清水1-4-4 城山公園内
⇒「白馬の森」「緑の窓」収蔵。
長野県諏訪市湖岸通り1-13-28
⇒「晩鐘」収蔵。
東山魁夷作品を収蔵している美術館【香川編】
香川県坂出市沙弥島字南通224-1
私が今後鑑賞したいと思った東山魁夷作品

今後私が観たいと感じる東山魁夷作品を列挙してみます。
| 残照 | 東京国立近代美術館 |
|---|---|
| 道 | 東京国立近代美術館 |
| 青響 | 東京国立近代美術館 |
| 白夜行 | 東京国立近代美術館 |
| 冬華 | 東京国立近代美術館 |
| 年暮る | 山種美術館 |
| 晩鐘 | 北澤美術館 |
| 緑響く | 長野県信濃美術館 東山魁夷館 |
| 白馬の森 | 長野県信濃美術館 東山魁夷館 |
| 緑の窓 | 長野県信濃美術館 東山魁夷館 |
まとめ
- 日本を代表する人気日本画家
- 皇居新宮殿の「朝明けの潮」や唐招提寺の障壁画を制作
東山魁夷の世界にたっぷりとひたってみたいものですね。
■関連書籍のご案内です。
↓