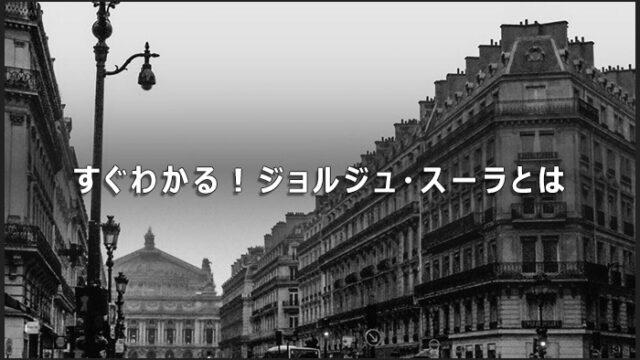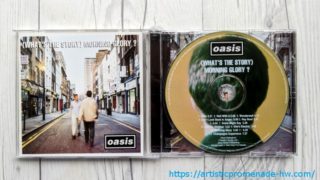レンブラント・ファン・レインは、オランダ・バロック絵画を代表する画家のひとりです。それにとどまらず、ヨーロッパ絵画史を語るには外せないほどの存在でした。
レンブラントは、写実的技術の高さや「光と影」を絶妙に表現する技法の名手でした。「光と影の魔術師」「光と影の画家」といった異名の持ち主です。
油彩画だけでなく、銅版画やエッチングの技術にも秀でていました。
ここではレンブラントの生涯を、わかりやすくご紹介します。
レンブラントの誕生~学生時代まで
 オランダ・ライデン
オランダ・ライデンレンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レインは1606年(慶長11年)7月15日、ネーデルラント連邦共和国(現在のオランダ)のライデンで誕生しました。
父親ハルマン・ヘリッツゾーン・ファン・レインは中流階級の出身で製粉業を営んでいました。母親の実家はパン屋でした。
1613年(慶長18年)、レンブラントはラテン語学校に入学します。レンブラントは成績優秀だったのでしょう。1620年(元和6年)には飛び級でライデン大学の哲学部に入学しました。
両親もレンブラントには製粉業を継ぐようには期待しなかったようです。家業は兄が継ぎました。
両親から法律家になるように期待されたレンブラント。しかし…ライデン大学への在籍期間はわずか数ヶ月。その理由は、画家を志したからでした。
レンブラント、画家を目指す
 オランダ・アムステルダム
オランダ・アムステルダム17世紀のオランダ・ライデンには美術を教える学校はありませんでした。そこでレンブラントは、歴史画家ヤーコプ・ファン・スヴァーネンブルフに弟子入りすることを決意します。
スヴァーネンブルフからは、絵画の基礎的な技法や解剖学などを学びました。その期間は約3年間です。
1624年(元和10年・寛永元年)の約6ヶ月間、レンブラントはアムステルダムの歴史画家ピーテル・ラストマンに師事します。ラストマンからは光の明暗を用いるカラヴァッジョ派の技法や表現方法などを学びました。ラストマンはレンブラントに大きな影響を与えました。
レンブラントは、ドイツ・ルネサンス期の画家アルブレヒト・デューラーの著書「人体均衡論」を通じて、絵画の描写力に活用しました。
レンブラント、ライデンへ戻る
 オランダ・ライデン
オランダ・ライデンアムステルダムからライデンへと戻ったレンブラントは、アトリエを構えます。
1625年(寛永2年)、レンブラントは「聖ステバノの殉教(聖ステバノの石打)」を制作します。
ライデンでは同門(ラストマンの弟子)のヤン・リーフェンスと知り合います。ヤン・リーフェンスはいわば、レンブラントのライバル的存在でした。
1628年(寛永5年)には弟子を取るようになったレンブラント。絵画やエッチングがヨーロッパに販売されるようになり、レンブラントの名が世に知られるようになりはじめました。
レンブラント、再びアムステルダムへ
 WikiImagesによるPixabayからの画像:レンブラント「テュルプ博士の解剖学講義」
WikiImagesによるPixabayからの画像:レンブラント「テュルプ博士の解剖学講義」レンブラントの生きた時代、画家として成功するならイタリアで研鑽を積むことが必須でした。しかしレンブラントは、イタリア行きは考えていなかったようです。
画家としての成功を実感し始めていたレンブラント。1630年(寛永7年)に父親が他界し、翌年には再びアムステルダムへと向かいます。
肖像画をメインに描いていたレンブラントのもとに、1632年(寛永9年)に集団肖像画の依頼が届きます。医師であるニコラス・テュルプが解剖する場面を描いた「テュルプ博士の解剖学講義」により、レンブラントの評判は高まりました。
アムステルダムで結婚したレンブラントは、アムステルダム市民と認められ聖ルカ組合(芸術家のギルド)のメンバーになります。
それまで間借りしていたレンブラントでしたが、1639年(寛永16年)に邸宅を購入します。奥さんの財産を食いつぶしていると揶揄されていたようです。
画家としての名声だけでなく富も得ていたはずのレンブラントが、大きな買い物(自宅)や投機に金銭を費やしていたのは意外な感じがします。
レンブラントの代表作「夜警」とその時期の状態
 WikiImagesによるPixabayからの画像:レンブラント「夜警」
WikiImagesによるPixabayからの画像:レンブラント「夜警」1642年(寛永19年)、レンブラントは「フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ライテンブルフ副隊長の市民隊」を制作します。この作品は、年月の経過とともに表面が茶色く変色してしまい、いつしか「夜警」として広く知られるようになりました。
現在アムステルダム国立美術館に展示されている「夜警」は、レンブラントの代表作であると同時にオランダ絵画の絶頂期を彷彿とさせる作品です。
レンブラントが「夜警」を制作している時期は、彼にとって辛い時期でもありました。息子と二人の娘、それに母を失い、妻が病気になって寝込んでしまったのです。レンブラントの奥さんの死因は結核だと考えられていますが、29歳の若さで亡くなりました。
少しだけレンブラントの仕事面に目を向けてみましょう。
レンブラントの時代は、顧客の注文を受けて絵を制作するスタイルが一般的でした。ところが、レンブラントの絵画に対する芸術性の探求が、必ずしも顧客の満足と一致していたわけではありませんでした。
肖像画を注文する顧客にしてみれば、自分の姿をハッキリと描いてほしいと思うのが普通でしょう。しかし「光と影の画家」と言われたレンブラントの肖像画は、顧客が望むような肖像画でないことがあったのです。その結果、レンブラントに対する不満も聞かれるようになっていきました。
これまでお伝えしたように、レンブラントに対する肖像画の依頼者は減少傾向に転じてしまいます。
そこでレンブラントは、聖書を題材とした作品も描くようになりました。
これによって受注制作ではなく、完成した作品を販売する方法(現在の個展に近いスタイルでしょうか?)にも取り組みました。17世紀のオランダでは、珍しい販売形態でした。
レンブラントの浪費癖と晩年
 オランダ・アムステルダム
オランダ・アムステルダム巨額な邸宅の購入や投機で失敗していたレンブラントですが、他にも絵画や版画、骨董品などを収集する浪費癖がありました。消費を上回る収入があれば問題なかったのでしょうが…
さらには婚約にまつわる訴訟もあり、レンブラントの制作活動にも暗い影を落としました。自身の金銭感覚の欠如や仕事の減少により経済的困窮状態となってしまいました。
結局レンブラントは、収集した美術品などを手放すことで何とか生活を維持していたのです。
レンブラントの債権者たちは、1652年(慶安5年・承応元年)に勃発した英蘭戦争の影響で経済状況が悪化したことで取り立てを厳しくしていきます。1656年(明暦2年)には破産の申し立てを行い、裁判所の指示によりレンブラントは財産を競売にかけ現金化し返済するように命じられたのでした。
1660年(万治3年)頃、邸宅を手放したレンブラントは貧民街へと移ることに…
さらにレンブラントは、画家ギルドにより画家とみなされなくなってしまいます。それは一般的な形での絵画制作の受注ができなくなることを意味していました。
そのような状況にもかかわらず、レンブラントの絵画への情熱は冷めることはなかったようです。
レンブラントは1669年(寛文9年)10月4日にアムステルダムで亡くなりました。
レンブラントの作品名紹介
 レンブラント像
レンブラント像レンブラントの作品名のいくつかをご紹介します。
| 1627年 (寛永4年) |
「愚かな金持ちの譬え」 【ベルリン国立絵画館所蔵】 |
|---|---|
| 1630年 (寛永19年) |
「悲嘆にくれる預言者エレミヤ」 【アムステルダム国立美術館所蔵】 |
| 1632年 (寛永9年) |
「テュルプ博士の解剖学講義」 【マウリッツハイス美術館所蔵】 |
| 1636年(?) (寛永13年?) |
「使徒パウロ」 【ウィーン美術史美術館所蔵】 |
| 1638年 (寛永15年) |
「善きサマリア人のいる風景」 【チャルトリスキ財団[クラクフ国立美術館]所蔵】 |
| 1639年 (寛永16年) |
「石のてすりにもたれる自画像」 【アムステルダム国立美術館版画素描室所蔵】 |
| 1642年 (寛永19年) |
「フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ライテンブルフ副隊長の市民隊」 【アムステルダム国立美術館所蔵】 ※「夜警」として有名。 |
| 1648年頃 (正保5年・慶安元年頃) |
「病人たちを癒すキリスト(100グルデン版画)」 【国立西洋美術館所蔵】 |
| 1651年 (慶安4年) |
「マグダラのマリアの前に現れるキリスト」 【ブラウンシュヴァイク、ヘルツォーク・アントン・ウルリヒ美術館所蔵】 |
| 1653年 (承応2年) |
「三本の十字架」 【アムステルダム国立美術館版画素描室所蔵】 |
| 1660年 (万治3年) |
「修道士に扮するティトゥス」 【アムステルダム国立美術館所蔵】 |
| 1660年 (万治3年) |
「聖ペテロの否認」 【アムステルダム国立美術館所蔵】 |
まとめ
- レンブラントは、オランダ・バロック絵画を代表する画家のひとり。
- 「光と影の画家」と呼ばれている。
- 生前から有名だったが、浪費癖もあった。