はじめまして。
わたなびはじめです。
ここではわたなびはじめの自己紹介をさせていただきます。
わたなびはじめという平凡な田舎少年

私は北海道函館市で生まれ、高校卒業までを過ごしました。
生まれて間もなく母と二人暮らしが始まり、父の顔を知らずに過ごしていました。
私が物心ついたあとに父と会ったのは、母の葬儀のときでした。
親子二人の生活は私にとっては普通のことで、不都合を感じたことはありませんでした。
母の努力と周囲の方々のご厚意が大きかったことは、大人になってから認識できるようになりました。
幼い頃は神経質で、「人の顔色ばかり気にしている」と思われていたようです。
私にとっては無意識の防衛術だったのかもしれません。
身体はヒョロヒョロで運動音痴。
保育園では毎朝のように、母との別れの際に泣きわめいていた記憶が残っています。
母の仕事の都合で保育園の帰り時間は遅くなることが多く、先生の部屋で一人で遊んで待っていることも多かったですね。
寂しがり屋の性格はその後も続き、小学校に上がっても、クラスではいるのかいないのかわからないほど暗い存在でした。
放課後に野球をやっても、同い年の友人たちのようにはプレイできず足を引っ張るばかり…。
それなりに友人はいましたが、人とのコミュニケーションは得意とは言えませんでした。
ひ弱だった少年が中学で剣道部に

ひ弱だったこともあり、中学校に入学したら部活動をしようと思いました。
選んだのは剣道です。
理由といえば、球技は脚が遅いし、ボールは怖い、チームプレーなど無理だと判断したからです。
柔道部も考えたのですが、痛そうなのでやめました。
私は運動が苦手だったので全く分かっていなかったことがあります。
それは、「運動部に入れば身体が強くなる」と勘違いしていたこと。
確かに身体は鍛えられます。
しかし運動部で活躍できるようになるためには、基礎体力をつけるために部活動とは別の時間を割かなければならないのです。
私にできたことといえば、サボらずに継続したことくらいです。
強くもなれませんでしたし、活躍もできませんでした。
実際、中学最後の退会では全敗しました。
せっかくだから、高校でも続けようと思いました。
高校での部活は断念、帰宅部員に

高校は進学と就職が半々くらいの学力の学校でした。
結果的に、母と同じ高校に入学しました。
母の時代は優秀だったそうですが、私の頃はそうでもありませんでした。
あれだけ続けようとしていた剣道でしたが、勝手に周囲についていけないと考えてしまい入部すらしませんでした。
もしかすると、中学時代にできないながらも頑張ったのだと自己満足してしまったのかもしれません。
授業が終わると帰宅する生活を3年間続けることになりました。
学業の方も優秀だったわけではなく、数学は全くわかりませんでした。
中学時代の部活と違って、勉強については継続するチカラが圧倒的に不足していました。
中学生の頃、母からは経済的に高校までしか行かせられないと言われていました。
私も高校まで行かせてもらえるだけで十分ありがたく思っていました。
高校卒業と同時に理由もなく、「自分は東京に行く」と思っていました。
札幌でも仙台でもなく、なぜ東京だったのか、本当によくわかりません。
当時はバブル景気の影響も多少はあったのでしょう。
高校の進路指導室には、東京の会社の求人もありました。
恩師のアドバイスで世界が開ける
高校3年生の頃には、当然のように進路の話がでてきます。
私は就職で上京するつもりでしたが、担任の先生との話で思ってもいなかった選択肢が目の前に現れたのです。
それは大学進学についてでした。
仕事をしながらでも大学生になれる可能性があるというのです。
大学進学など学力的にも経済的にも無理だと思っていたので、ろくに調べもせずにいた私。
通信制大学や夜間大学があることすら意識していませんでした。
あることは知ってはいましたが、自分とは関係が無いと思っていました。
通信制大学では、私の性格では継続できないと思い、夜の時間帯に通う大学を調べました。
ワクワクする反面、これから勉強しても間に合わない可能性をひしひしと感じていました。
大学受験は1校のみ。
すでに就職が決まった人を対象とした「有職者社会人枠?」で受験しました。
一般の試験の他に、作文の提出もありました。
東京までの往復は寝台列車。
安いホテルは満室状態だったので、少し高めの新宿歌舞伎町のホテルに宿泊することに。
受験とは言いつつも、ほとんど旅行感覚でした。
試験も自信のあった日本史ですら、全く歯が立たず…。
不合格を確信し、帰りの列車に間に合うことだけを考えていました。
それでも、いい経験をさせてもらったと思っていました。
なぜなら、大学受験なんてすることはないと思っていたのですから。
それからしばらくして、受験した大学から郵便物が届きました。
「不合格でも連絡がくるんだ~」と思いつつ開封したところ、「合格」の文字が…。
目を疑いましたが、合格通知でした。
私以上に、母の方が喜びは大きかったことでしょう。
息子が大学に行くなんて想像もできなかったはずですから。
仕事も夜間大学にも理解を示してくれる職場で、江戸川区に社員寮がありました。
このようにして北海道民から東京都民になったのでした。
可能性を広げてくださった高校3年時の担任の先生には、心から感謝しています。
仕事と夜間大学の両立に戸惑う
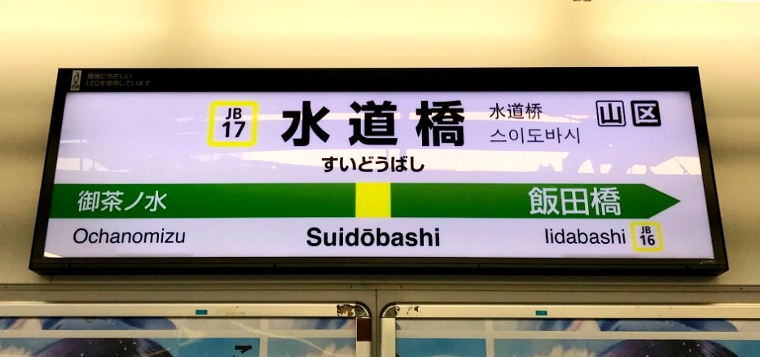
上京したての頃、田舎との違いに驚くばかりでした。
社員寮の水道をひねってうがいをしようとしたら、水が臭くてできませんでした。(失礼なことを書いてごめんなさい。)
現在は、東京の水も美味しくなっていると思います。
毎日、普通に飲んでいますから。
驚いたのはそればかりではありません。
朝の電車の混雑具合が尋常ではないことにも度肝を抜かれました。
そんなこんなで、昼間は身体を動かす仕事をし、夕方から大学の授業を受けに水道橋まで通う生活が始まりました。
しかし私にとっては簡単なことではありませんでした。
記憶によれば、授業は平日2コマ受けられたと思います。
ところが1コマで帰ることが多くなり、気が付けば単位をかなり落としていました。
3年になる前に、学校に呼び出されました。
やる気がないことを咎められるのかと思っていたところ、そうではありませんでした。
優先的に再履修の科目を取れるように配慮していただいたのです。
ちなみに英語と必修の簿記は単位を落とし続けていました。
もしも、一定の単位を取得しなければ進級できない制度だったなら、私の学生生活は大きく後退していました。
全て自分の責任です。
3年、4年は心を入れ替えて学業に励みました。
その頃には、仕事も変わっていました。
記憶に残っているのは4年生のときのことです。
4年時には平日2コマ、土曜日4コマの計14科目を履修していました。(最大限の履修です。)
しかも13科目で単位をとらなければ、卒業できなかったのです。
無事に4年間で大学を卒業したものの、特に就活はしていませんでした。
就活する時間もありませんでしたし…。
私には2年間ボランティアに行く計画がありました。
末日聖徒イエス・キリスト教会の宣教師になりたかったのです。
魅力的な同世代の人たちが集まったアルバイト先も辞め、ボランティアに出発しました。
良い影響をくれたさまざまな人達との出会いに感謝
ここでは、私の出会いを中心に話を進めたいと思います。
「魅力的な同世代の人たちが集まった」と形容したアルバイト先には、映画監督を目指している人やバンド活動をしている人、武術・忍術を学んでいる人、サーフィンの好きな人など、それまでに出会ったことのない人達がいました。
とても刺激的でした。
私がいろいろな本を読むようになったのも、絵画を美術館に観に行くようになったのも、この頃からです。
音楽については少し遡りますが、母の影響でカラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の「ボレロ」が好きでした。
もちろん、Boowyや氷室京介も大好きでした。
これはおぼろげな記憶なのですが、北海道にいた頃の母子のエピソードをご紹介します。
あるとき母がラジオから流れる曲についてスゴイ曲じゃないかと同意を求めてきたことがありました。
それがレッド・ツェッペリンの「天国への階段」だったのです。
当時の私には「天国への階段」が暗い曲としか思えず、全く興味をそそられませんでした。
母曰く「あのカラヤンも認めた曲なのよ!」と言っていました。
この記憶が自然に捏造されたものでなければ、こんなやり取りをしたはずです。
「天国への階段」は、今では私の一番好きな曲になっています。
不思議なことですが、母の影響を何年か越しに感じた経験は他にもあります。
司馬遼太郎の作品もそうです。
「燃えよ剣」はその最たるもので、幼い頃からその背表紙を見続けていたのに読もうとせず、函館を離れてから好きになりました。
「菜の花の沖」も同じような感じです。
ともに、函館と関係がある人物が主人公です。
私が絵画に興味を持ったキッカケは、1994年に国立西洋美術館で開催された特別展「バーンズ・コレクション展」でした。
そのときから図録収集が始まりました。
当ブログでも、ご紹介してくことになると思います。
母が他界し、私が結婚してからもこの趣味は続いています。
若い頃のスタンスとは違いますが…。
図録収集に関しては、私が母から影響を受けていたように、私の子供にとって良い影響になればいいとの思いも加わりました。
今のところ、思ったようにはなっておりません。
ですが、美術全集のようなモノを高額で購入することはできなくても、ときどきの図録収集を続けていればそれなりになるだろうと思っていました。
事実、引越では大変重たい荷物になりました。
家族でクラシックコンサートにも出かける機会がありました。
何度か行かせていただいたのが、川端成道さんのバイオリンコンサートです。
このブログは、絵画や美術館めぐり、クラシック音楽、UKロックをメインに話を進めていきます。
私の勝手な感想なども多々含まれると思いますが、よろしければお付き合いください。
ストレスの怖さを知らないがゆえの落とし穴
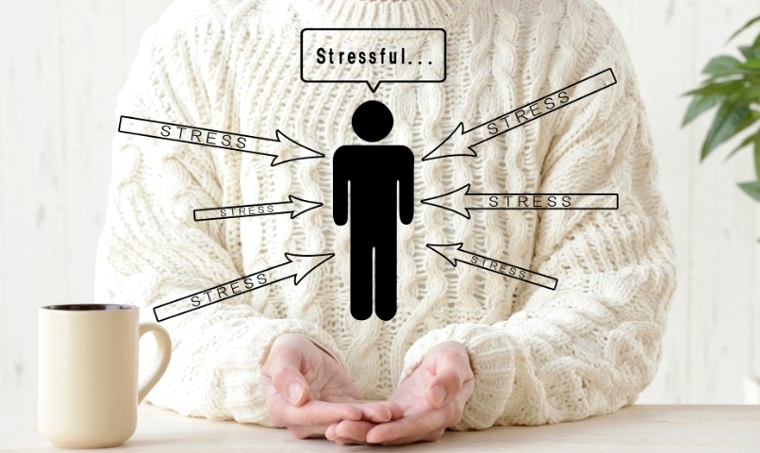
話を私の紹介に戻しますね。
現在の私は、市販の履歴書には書ききれないくらいの職歴があります。
その理由は、うつ病を患ってから、転職を繰り返すことになったからです。
私は「ストレス」が人に与える影響の恐ろしさを自覚せずに生きていました。
「ストレス発散なんて、何の意味があるの?」
「ストレス発散しても、状況は変わらないでしょう。」
と思っていたのです。
事実、ストレスを発散しただけでは困難な状況は変わらないかもしれません。
ですが、困難な状況に臨む自分自身の状態によって、結果が左右されることはあります。
これに気が付くまでに、生まれてから30年以上かかりました。
仕事に行かなければならないと思っているのに、体が言うことをきかないというか、外に出られなかった時期が何度もありました。
目がグルグル回って、横になっているのに気持ち悪いことも多々ありました。
病院に行きたくても行くことができないのです。
その後、症状がある程度落ち着いてから病院に行っても、大変さが伝わりません。
いくつか病院をまわったのですが、原因がわからなくて辛い時期を過ごしました。
その後も脳のMRIを撮ったり、耳鼻科で検査を受けたり、脳圧を下げる薬を飲んだりもしました。
大きな病院も含めていろいろな病院に行き、検査を受けましたが、どこも悪くないと言われます。
結局は心療内科で「自律神経失調症」と診断され、3週間ほど仕事に対するドクターストップを受けました。
そして症状は悪化し、「うつ病」と診断されました。
私は現在もうつ病の治療を受けています。
単に仕事の影響だけではなかったのだと思います。
私生活でも辛いことはありましたから。
一度は、完治したと思われたうつ病も再発してしまいました。
妻はパニック障害を患っています。
仕事でご迷惑をかけてしまった皆さまには本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
それでありながら、私を理解しサポートしようとしてくださった方々には感謝し尽くせません。
これからも「うつ病」とは長く付き合うことになると思います。
夫婦で精神的な病気になったことは、辛いことではありましたが、今ではお互いへの理解が深まっているように思っています。
子供にとっても、両親が病気なのですから負担を掛けていたことは間違いありません。
うつ病の症状については波があると思います。
それでも、今では以前に比べるとよくなってきている気がします。
医師の目から見たらまだまだかもしれませんが…。
このようにブログも書こうと思えるようになってきたのですから、前向きに考えていきたいと思っています。
うつ病ではあるけれど在宅ワークに取り組みつつブログを更新
現在は、会計関連の在宅ワークを行なっています。
アフィリエイトにも取り組んでいます。
このブログには「芸術的散歩道」というタイトルを付けました。
とはいえ、私はこれまでに専門的な芸術教育を受けたことはありません。
芸術好きというだけです。
ですが、きっとこれからも美術館に行ったり、レコードを聴いたりしながら記事を書いていくと思います。
負担にならない範囲で本も読むかもしれません。
自分の現状の身の丈に合った範囲で、楽しみながらブログを継続していくつもりです。
絵画、美術館、クラシック音楽、UKロックの評価基準 by わたなびはじめ

最後に、絵画、美術館、クラシック音楽、UKロックの評価基準について触れておきます。
個人的な基準ですがご了承ください。
絵画の評価基準
私が絵画をみる際の基準は、「欲しいか欲しくないか」です。
とても乱暴で贅沢な基準かもしれませんね。
実際、美術館で展示されるような絵画は購入できません。
そういう意味ではなく、「自分の家に飾りたい絵かどうか」という意味合いです。
ステキと思っても、美術館で展示された方が絶対によい絵画がほとんどです。
ですが、稀に「自分の家に飾ってみたいな~」と思う作品もあるのです。
絵画についてはこのような視点で観ていますので、専門的なことはご紹介できないと思います。
美術館の評価基準
美術館の評価基準は、「居心地の良さ」です。
落ち着きけて、ボーっとできるスポットがあったりすると、俄然評価は上がります。
全て個人的主観ですので、ご了承ください。
クラシック音楽の評価基準
クラシック音楽については、好きな指揮者が第1基準です。
好き嫌いが分かれるとは思いますが、私は指揮者としてのヘルベルト・フォン・カラヤンが大好きです。
カラヤンとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の組み合わせが基本的に好きです。
もう一人、注目している指揮者がいます。
グスターボ・ドゥダメルです。
何度も来日されていますが、残念ながら未だ生演奏を聴いたことがありません。
クラシック音楽では、イベントにも注目しています。
イギリスのプロムス、ベルリン・フィルのジルベスターコンサート、ウィーン・フィルのニュー・イヤー・コンサートなどです。
NHKのBS放送を楽しみにしています。
UKロックの評価基準
UKロックについては評価云々ではなく、単に好きなことをご紹介します。
上述のレッド・ツェッペリンをはじめ、オアシス、MUSE(ミューズ)といったバンドが中心になると思います。
バンドとして現役活動をしているのはMUSE(ミューズ)だけですね。
レコードのUK初盤についてやリマスター版などについても触れられたらと思います。
わたなびはじめの芸術的散歩道をよろしくお願いします
長い自己紹介となりましたが、リハビリとストレス解消的な位置づけでもありますので、のんびりとお付き合いいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
わたなびはじめ



