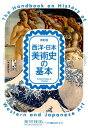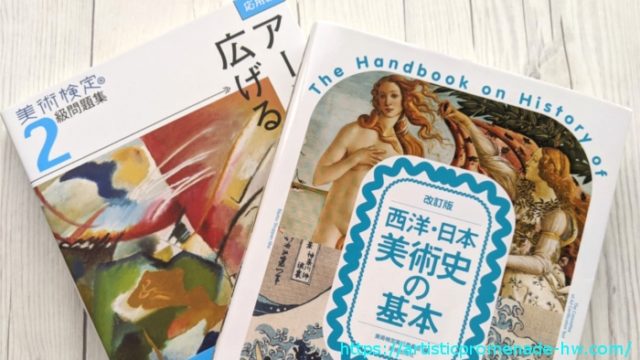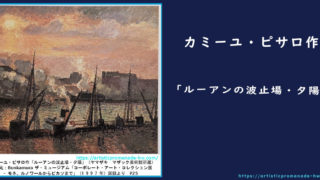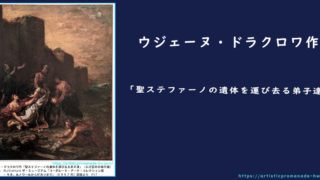美術検定2級合格のための学習を通じて学んだことをご紹介するシリーズ。
中世美術編の2回目です。今回は「中世初期&ロマネスクの美術」です。
美術検定の公式テキスト「改訂版 西洋・日本美術史の基本」では、「中世初期の美術」と「ロマネスクの美術」は区別して解説されています。それぞれ、1ページ強のボリュームです。
なぜ、「中世初期の美術」と「ロマネスクの美術」を合体させたのかというと、ご紹介できそうな画像を見つけられなかったからです。
特に「中世初期の美術」は、聖書の装飾された写本などが扱われています。写本などの画像はご紹介できませんが、ご了承ください。
この記事でご紹介している画像は、私のセレクト・ミスなどにより本物の画像ではない可能性がありますのでご了承ください。
あらかじめご了承ください。
中世初期&ロマネスクの美術・概要
中世とはいつ間から始まるのか?
これにはいくつかの見方があるのかもしれませんが、一般的な見方をご紹介します。
西ローマ帝国の皇帝ロムルス・アウグストゥルスが紀元476年に廃位し、西ローマ帝国が滅んだとことが区切りとなります。これにより「古代」が終わりを告げ、「中世」と呼ばれる時代に突入します。
西ローマ帝国滅亡後、現在のドイツ西部やベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スイス、オーストリア、スロベニア、フランス、イタリア北部といった地域にはゲルマン民族によるフランク王国(フランク帝国やカロリング帝国とも呼ばれる)が建国されます。
フランク王国はキリスト教(ローマ・カトリック教会)を受け入れます。さらに王が即位する際には、教皇による聖別が行なわれていました。
フランク王国には2つの王朝ができました。初期はメロヴィング朝が、その後はカロリング朝が統治します。
こういった状況が中世の美術にも大きく影響を与えることになるのです。
中世初期の美術・メロヴィング朝
メロヴィング朝を興したクロービズ王は、ローマ帝国への畏敬の念が強かったようです。ゲルマン民族の王朝です。宗教ではキリスト教を受け入れたり、公用語をラテン語(ローマで話されていた言語)にしたりしました。
メロヴィング朝時代の美術については、工芸品や聖書の写本といった豪華な装飾が残っています。
画像は用意できませんでしたが、代表的な美術品名をご紹介します。
- ヒルデリーヒ1世の宝物【480年頃】
- リンディスファーンの福音書・十字架の頁【8世紀頃】
- モノグラムXPI「ケルズの書」【800年頃】
写本の普及には、6世紀頃から建設されていった修道院の存在が大きかったようです。特にアイルランドの修道院では、豪華な写本が作られました。
中世初期の美術・カロリング朝
メロヴィング朝に次いでカロリング朝を興したのはピピン3世です。
紀元800年(延暦19年)には、ピピン3世の子であるカール大帝(カール1世、シャルルマーニュとも呼ばれる)が、フランク王にして西ローマ皇帝となります。
カール大帝も古代ローマの復興に対する思い入れが強かったようです。
美術・建築に関しては、修道院や教会堂、学校の建設が行なわれ、ローマ美術にケルトやゲルマン、ビザンティンといった要素が融合した独自の発展を生み出すことになりました。
カロリング朝の代表的な美術品名をご紹介します。
- 福音書書記者聖マルコ像「アダの福音書」【800年頃】
- リンダウの福音書の装丁表板【870年頃】
カール大帝が亡くなると、843年(承和10年)にヴェルダン条約によりフランク王国は分裂してしいます。
中世初期の美術・ザクセン朝(オットー朝)
フランク王国分裂後、ヨーロッパ北部・西部地域はバイキング(海洋民族)に襲われます。一方、ヨーロッパ南部はイスラム勢力が、東からはスラブ人やマジャール人が侵攻してきます。
962年(応和2年)、オットー1世が神聖ローマ帝国皇帝に即位します。オットー1世はカール大帝の意志を継承しようとしました。
ザクセン朝(オットー朝)の代表的な美術品をご紹介します。
- ゲロのキリスト磔刑像(ケルン大聖堂)【975~1000年頃】
- ペテロの足を洗うキリスト「オットー3世の典礼用福音書」より【10世紀末頃】
ロマネスクの美術
「ロマネスク」の意味について、美術検定の公式テキストには次のような記述があります。
「ロマネスク」にはローマ風という意味があります。この美術が栄えた11世紀から12世紀は、社会的に大きな変革があった時代です。
出典:『西洋・日本美術史の基本改訂版』美術検定実行委員会 59ページ
社会的な大きな変革には、次のようなことが考えられます。
- 封建制度の成立。
- 十字軍の遠征。
- ヴェネツィア、ジェノヴァ、ピサといった地中海貿易航路の再開。
このような社会背景が美術分野にも影響を与えていたと言えます。
ヨーロッパ南部では修道院が多く建設されました。
また、教会堂の扉口の構成要素として、半円形の壁面「タンパン」に聖書を主題とした彫刻が施されました。
ロマネスクの美術の代表的な作品・建築名をご紹介します。
- クリュニー修道院(フランス)【900年頃】
- サン=セルナン聖堂【1080~1120年頃】
- 使徒(サン=セルナン聖堂の建築彫刻)【1090年頃】
- 栄光のキリスト(タウルのサン・クレメンテ教会後陣フレスコ)【1123年頃】
- 使徒たちに布教の使命を授けるキリスト(サント=マドレーヌ大聖堂 西側正面タンパン浮彫彫刻)【1120~1130年再建】
- 獅子像(ドイツ・ブラウンシュヴァイク)【1166年】
- ピサ大聖堂(イタリア)【11~14世紀】
やはり修道院による聖書の写本は盛んだったようです。
「24人の長老(サン・スヴェールの黙示録)【11世紀中頃】」のように、聖書の挿絵や装飾が残っています。
ロマネスクの美術の作品紹介
中世初期の美術作品や建築物はご紹介できませんが、ロマネスク美術の建築を中心にお伝えします。
ロマネスクの美術・ピサ大聖堂
ピサ大聖堂よりも「ピサの斜塔」の知名度の方が高いのではないでしょうか?
ピサ大聖堂は、イタリア・トスカーナ州にあるロマネスク時代を代表する建築物のひとつです。1987年(昭和62年)にはユネスコ世界遺産(文化遺産)にも登録されています。
ピサ大聖堂は「十字架型平面形」をしています。
「十字架型平面形」とは、身廊と側廊が長方形に収められていて、そこに翼廊を直角に張り出させることで、十字架型にしたものです。
建築材料には、石やレンガ、大理石などが用いられています。
ロマネスクの美術・クリュニー修道院
フランス・ブルゴーニュ地方クリュニーに、紀元900年頃に建てられた修道院です。
クリュニー修道院はフランス革命により破壊され、他の建造物の材料として用いられた経緯があるため、当時の姿を残しているのは聖堂南側の翼廊の一部だけとなっています。
画像右奥の2つの塔の辺りだと思われます。
ロマネスクの美術・獅子像
 Mac_PaverickによるPixabayからの画像:獅子像
Mac_PaverickによるPixabayからの画像:獅子像ザクセンのハインリヒ獅子公が、ブラウンシュヴァイク(ドイツ)にある自身の宮殿前に設置したものです。
この獅子像は青銅製です。大きさは長さ約1.8mと、ほぼ実物のライオンくらいのサイズです。
「ブラウンシュヴァイク」と聞くと、銀河英雄伝説の登場人物「オットー・フォン・ブラウンシュヴァイク公爵」を連想してしまうのは、私だけでしょうか?
まとめ
- 聖書の写本に対する挿絵や装丁装飾が行なわれた。
- ロマネスクを代表する建築物としてピサ大聖堂は有名。
■参考文献
- 「改訂版 西洋美術の歴史」監修 横山勝彦、半田滋男/編集 美術検定実行委員会/発行 美術出版社
- 「西洋美術の歴史」著者 H・W・ジャンソン、アンソニー・F・ジャンソン/訳者 木村重信、藤田治彦/発行 創元社
■関連書籍のご案内です。
↓