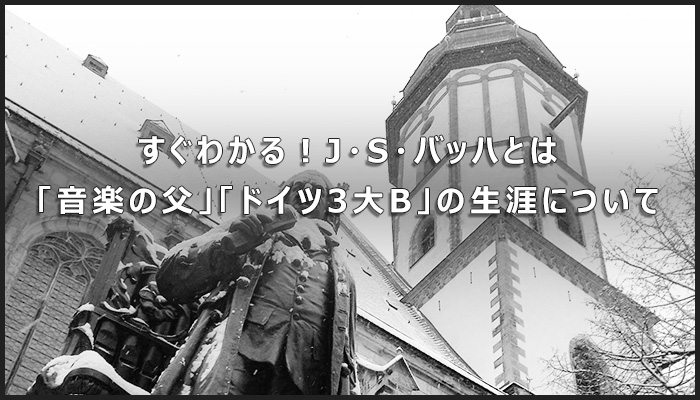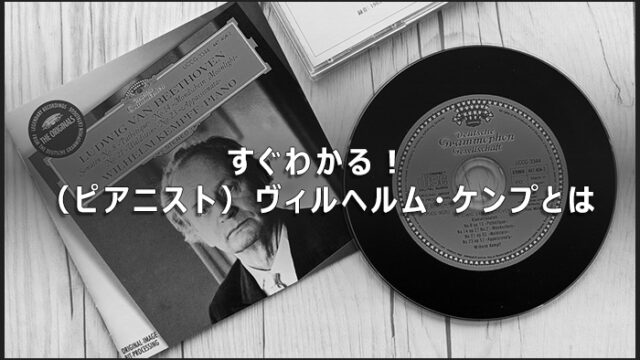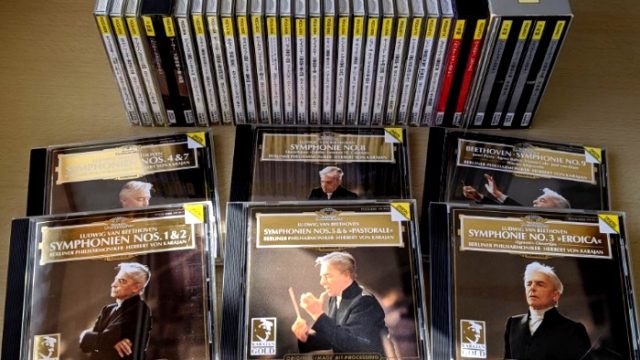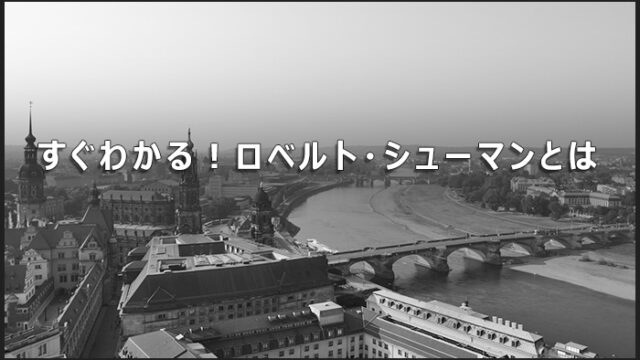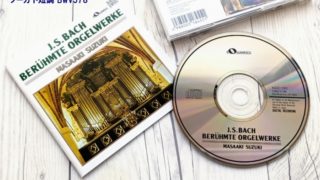18世紀に音楽家・作曲家・オルガニストとしてドイツで活躍したヨハン・セバスティアン・バッハ(J・S・バッハ)。ヘンデルやヴィヴァルディと共にバロック音楽を代表する音楽家のひとりです。
J・S・バッハは西洋音楽の基礎を築いた人物であるとされ、日本では「音楽の父」と呼ばれています。ベートヴェンやブラームスと共に「ドイツ3大B」のひとりでもあります。
極端な表現になるかもしれないけれど、バロック音楽はJ・S・バッハの死をもって終了したとも言えるんだよ。
J・S・バッハの音楽は弟子らに継承されてはいましたが、世間からは忘れられていきました。
バッハが再び脚光を浴びるきっかけは、19世紀になってからのこと。フェリックス・メンデルスゾーンが「マタイ受難曲」を上演するなどしてバッハ復興に励んだからでした。
バッハの死とほぼ時期を同じくしてバロック音楽の歴史は幕を閉じたとはいえ、それに続く古典派に分類されるハイドンやモーツァルト、ベートヴェンもその影響を受けているはずです。
バッハの子孫には音楽家が多く誕生しているため、区別のため「大バッハ」と呼ばれたりもします。
J・S・バッハ、誕生~音楽家への道のり
 パイプオルガン・イメージ
パイプオルガン・イメージJ・S・バッハは、1685年(貞享2年)3月31日に神聖ローマ帝国(現在のドイツ)・アイゼナハにて生まれました。バッハが生まれたのは、当時のドイツでは有名な音楽家の家系でした。
J・S・バッハが9歳のころに母親が他界し、父親は再婚しましたが間もなく亡くなっています。
10歳になる前に両親を亡くしたバッハは、14歳年長でオルガニストとして独立していた兄ヨハン・クリストフの元に引き取られました。
もしかすると、少しでも早く自立したかったのかもしれないね。
1700年(元禄13年)、バッハはリューネブルクの修道院に付属している学校の給費生になります。
1703年(元禄16年)には、ヴァイマル(ワイマール)の宮廷楽団に就職しました。ここではヴァイオリンを担当しましたが、オルガン奏者の代役を務めることもありました。
それだけでなく、アルンシュタットの新教会(現在:バッハ教会)に新しく設置されたオルガンの演奏者にも選ばれています。
バッハは向上心の強い人物でかつ勤勉。400kmも歩いて、有名な音楽家の演奏を聴きに行ったこともあったほどでした。
1707年(宝永4年)、ミュールハウゼンの聖ブラジウス教会のオルガニストの職に就いたバッハは、この時期にマリア・バルバラと結婚します。
音楽家としての評価は高かったバッハでしたが、この当時は経済的に楽ではありませんでした。
J・S・バッハのヴァイマル(ワイマール)時代
 ドイツ・ワイマール【マルクト広場】
ドイツ・ワイマール【マルクト広場】1708年(宝永5年)、ヴァイマルに戻ったバッハは、ザクセン=ヴァイマル公国の宮廷オルガニストの職を得ます。
さらにこの時期には作曲活動も活発で、オルガン曲を多数制作しています。
1713年(正徳3年)には、別の土地のオルガニストの求人に応募したこともあったんだ。
採用されたんだけれど、昇進と昇給で待遇面が改善されて思い留まったみたい。
しかし、結局は1717年(享保2年)にヴァイマルを離れることに。その理由は、アンハルト=ケーテン侯国宮廷楽長に就任したためでした。
J・S・バッハのケーテン時代
 ドイツ【ブランデンブルク門】
ドイツ【ブランデンブルク門】アンハルト=ケーテン侯国宮廷楽長に就任したバッハは、世俗音楽の名作を遺しています。作曲活動に励むことができた要因としては、大きく2つの理由が考えられます。
- アンハルト=ケーテン侯レオポルトは音楽に理解のある人物で、環境に恵まれていたこと。
- アンハルト=ケーテン侯国がカルヴァン派の教えを実践していたため、教会音楽の制作が求められなかったこと。
1720年(享保5年)、バッハは妻を亡くします。領主の旅行に伴ってケーテンを離れていたため、妻の死を看取ることができなかったバッハでしたが、1721年(享保6年)には再婚しています。お相手は、宮廷歌手だったアンナ・マクダレーナ・ヴィルケです。
1721年(享保6年)、バッハは「ブランデンブルク協奏曲」をブランデンブルク=シュヴェート辺境伯クリスティアン・ルートヴィヒに献呈しました。
この頃から、アンハルト=ケーテン侯国の宮廷楽団の予算・規模が縮小へと向かい始めます。どうやら王妃が音楽嫌いだったそうです。
J・S・バッハ、ライプツィヒへ
 ドイツ【ライプツィヒ中央駅】
ドイツ【ライプツィヒ中央駅】1723年(享保8年)、バッハはライプツィヒにある聖トーマス教会のカントル(キリスト教における音楽指導者、合唱長のこと)兼音楽監督に就任します。
この時期のバッハは教会音楽(教会カンタータなど)を中心に作曲活動に励みます。
1727年(享保12年)には、「マタイ受難曲」が聖トーマス教会で初演されています。
きっと、宮廷作曲家になりたかったんだね。
J・S・バッハ、宮廷作曲家就任とその晩年
 ドイツ・ライプツィヒ【トーマス教会 バッハ像】
ドイツ・ライプツィヒ【トーマス教会 バッハ像】1736年(享保21年・元文元年)バッハはザクセンの宮廷作曲家の職を得ます。
バッハはその晩年、病で苦しみます。
1749年(寛延2年)には脳卒中で倒れますが、何とか回復します。
しかし以前から患っていた内障眼の悪化により、視力はほとんどありませんでした。手術も2度受けますが結果は成功とは言えず、投薬で体力を奪われていきます。
病床に付していたバッハは、1750年(寛延3年)7月28日にライプツィヒにて亡くなりました。
J・S・バッハの代表曲
18世紀のドイツにおいて、音楽家の成功は次の2つの要素を満たすことでした。
- 宮廷楽長の地位を得ること。
- 歌劇(オペラ)を作曲すること。
バッハの作曲数は1000曲を超えると言われますが、その存命中に国外に名をとどろかせることはなく、ドイツの王様と教会のために曲を書き続けていたのでした。
ここでJ・S・バッハの代表曲をいくつか列挙してみます。
| 1700年代前半 | ブランデンブルク協奏曲第1番~6番 BWV1046~1051 |
|---|---|
| 1703年~1707年 (元禄16年~宝永4年) |
フーガ ト短調 BWV578 ※作曲時期については諸説あり。 |
| 1704年頃 (元禄17年・宝永元年頃) |
トッカータとフーガ ニ短調 BWV565 |
| 1717年~1723年頃 (享保2年~享保8年頃) |
ヴァイオリン協奏曲第2番 ホ長調 BWV1042 |
| 1722年~1723年 (享保7年~享保8年) |
平均律クラヴィーア曲集第1巻 BWV846~869 |
| 1724年~1749年 (享保9年~寛延2年) |
ミサ ロ短調 BWV232 |
| 1727年~1729年 (享保12年~享保14年) |
マタイ受難曲 BWV244 |
| 1734年 (享保19年) |
クリスマス・オラトリオ BWV248 |
| 1738年~1742年 (元文3年~寛保2年) |
平均律クラヴィーア曲集第2巻 BWV870~893 |
まとめ
- 西洋音楽の基礎を築いた人物で「音楽の父」と呼ばれている作曲家。
- ヘンデルと同じ年に誕生した。
- 1000曲を超える楽曲を制作した。