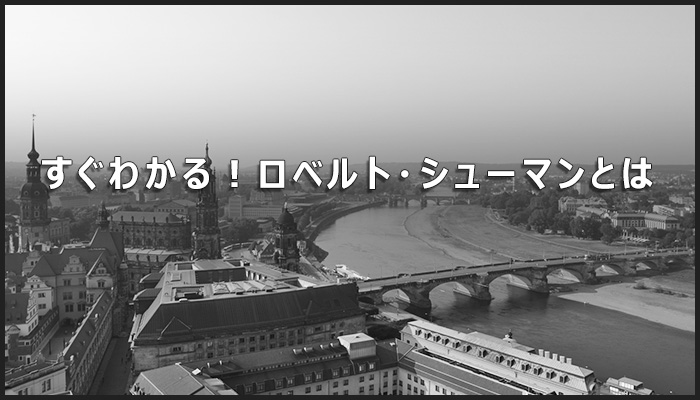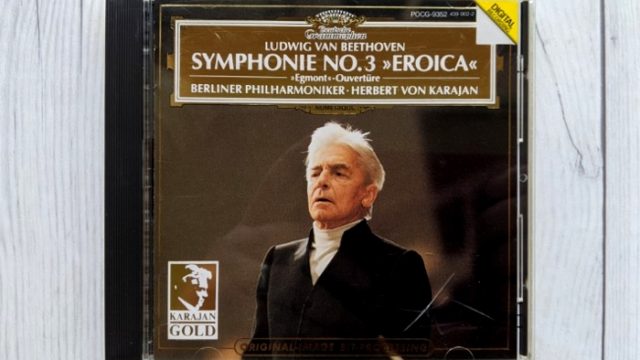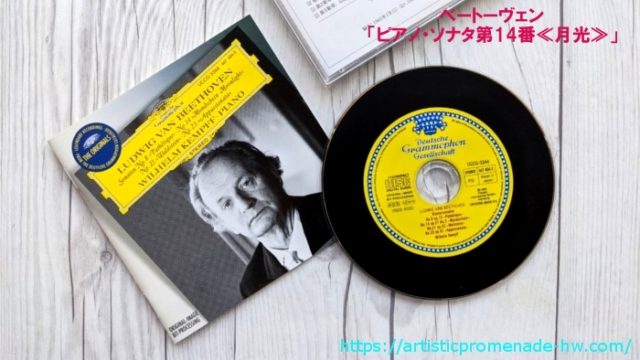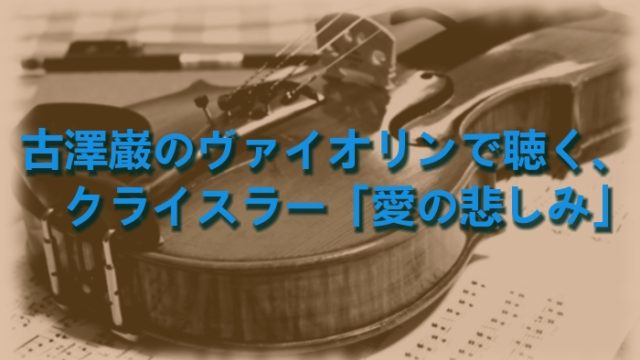19世紀ドイツ・ロマン派を代表する音楽家のひとりロベルト・シューマン。
交響曲も作曲していますが、シューマンといえば歌曲やピアノ曲が有名です。
シューマンは音楽評論家としても活躍しました。自ら音楽雑誌「新音楽時報」を創刊しています。
同時代に生きた音楽家には、ショパンやリスト、メンデルスゾーン、ベルリオーズ、ワーグナーがいます。
2021年(令和3年)の最初を飾る記事として、ロベルト・シューマンの生涯をわかりやすくご紹介します。
新型コロナウィルスの影響は未だ収束しておりませんが、十分に気を付けてこの一年を乗り切りましょう。
皆様の心が穏やかでありますよに。
わたなびはじめ
シューマンとは、誕生~青年時代
 ドイツ・ドレスデン【ザクセン宮殿】
ドイツ・ドレスデン【ザクセン宮殿】ロベルト・アレクサンダー・シューマンは、1810年(文化7年)6月8日にザクセン王国ツヴィッカウ(現:ドイツ)で誕生しました。
ムルデ川沿いにあるツヴィッカウは、ライプツィヒの南方に位置する工業都市です。
その歴史は7世紀頃にまで遡(さかのぼ)ることができ、開拓したのはスラブ人でした。
しかし、15世紀には火災により壊滅的な被害を受けます。
その後復興を果たしています。
時代を経て、第二次世界大戦前から自動車産業が盛んになった街です。
シューマンは5人兄弟の末っ子で、裕福な家庭に育ちます。父親は書店・出版業を生業(なりわい)としていていました。
両親は子供たちの教育に熱心だったのでしょう。シューマンには住込みの家庭教師がいました。6歳になると私立小学校に通い始めます。
シューマンが7歳の頃、父親に連れられてドレスデンに行き、ベートーヴェンの交響曲を聴く体験をしています。そのときの指揮者は、その数年後に歌劇「魔弾の射手」で有名になるカール・マリア・フォン・ウェーバーでした。
シューマンの音楽的才能は、この頃からその片鱗(へんりん)を見せ始めていました。小作品ではありますが、ピアノによる舞曲の作曲を行なっています。
その後もシューマンは、音楽に触れる機会を得ていたようです。1819年(文政2年)にはチェコのピアニスト兼作曲家のイグナーツ・モシェレスのピアノ演奏に感動し、ピアニストを志すようになります。また、ライプツィヒにてモーツァルトの歌劇「魔笛」も観劇しています。
1820年(文政3年)、シューマンはツヴィッカウの中等教育機関(ギムナジウム)に入ります。
そしてヨハン・ゴットフリート・クンチュよりピアノを学び始めるのでした。クンチュは聖マリア教会でオルガニストを務めていた人物です。
クンチュは、ハイドンやモーツァルト、ベートーヴェンといった古典派の音楽家たちの作品をピアノ連弾用に編曲して教えました。
父親により高価なシュトライヒャー製のピアノを買ってもらったシューマンは、即興的な演奏に何時間も没頭していたようです。
シューマンの父親は息子の音楽的才能を伸ばすことに熱心だったようで、ピアノの他にも指揮台などのオーケストラに必要な品々を提供していました。そのように熱心にシューマンを支援していた父親でしたが、1826年(文政9年)に他界しています。
ギムナジウムに通っていたシューマンは、音楽会やサロンにも迎えられ顔を出すようになります。シューマンは年上の人妻や同年代の少女2人と、ほぼ同じ時期に恋愛していたようです。
音楽的な才能だけでなく文才もあったシューマンは、詩や戯曲も書いています。
ベートーヴェン 交響曲第9番の「合唱」の原詩を書いたフリードリヒ・フォン・シラーや文豪ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテらの作品に情熱をもって親しんでいました。そのなかでもシューマンに大きな影響を与えたのは、「巨人」「生意気ざかり」などを書いたジャン・パウルでした。
シューマンとは、ライプツィヒ時代
 ハイデルベルク【シューマンが住んでいたアパート】
ハイデルベルク【シューマンが住んでいたアパート】1828年(文政11年)3月、シューマンはツヴィッカウのギムナジウムを卒業します。
その後はライプツィヒ大学の法科に進学します。
この頃シューマンは、友人とともにバイエルン王国の旅行をしています。旅の途中には、シューマンの尊敬するジャン・パウルの肖像画をその夫人がから譲り受けています。
旅行から戻り、学業に専念しようとしたシューマンでしたが、法律の勉強は彼には合いませんでした。徐々に授業への出席数も減ることに。
そのような状況で、シューマンはピアノを入手し、音楽仲間と室内楽を演奏することに情熱を燃やします。
とある音楽会でヴィーク父娘と出会ったシューマン。父親のフリードリヒ・ヴィークはシューマンのピアノの師となる人物です。
出会いといえば他に、ライプツィヒ歌劇場指揮者のハインリヒ・マルシュナーや楽譜出版商のホフマイスターといった人たちともつながりができました。
その後シューマンはハイデルベルク大学に転向します。表向きは有名な法科教授から講義を受けることを理由にしていましたが、実際のところ法律とは全く無縁の生活を送り、ピアノに没頭するのでした。
1829年(文政12年)5月、シューマンは故郷ツヴィッカウに戻る途中でフェルディナント・リースと会っています。
この頃になるとシューマンのピアノの腕前は広く知られるようになり始め、バーデン大公妃ステファニーの演奏会に招かれるほどになっていました。
1830年(文政13年・天保元年)、当時20歳だったシューマンは、ピアノ作品「アベッグ変奏曲」を作曲します。
同年、友人らとフランクフルトを旅行したシューマンは、ニコロ・パガニーニのヴァイオリン演奏を聴いて感動したのでした。
しかし...金銭面では家族だけでなく友人にも金を無心するほどの浪費癖がみられるようになっていました。もともと裕福な家庭で育ち、あまりお金に困ったことのなかったことが影響したのかもしれません。
シューマンの母親は、息子が音楽家になることには後ろ向きな見解を持っていました。音楽で生計を立てられるのか?というのが理由です。そのため大学進学時には、法律を学ぶように勧めたのでした。
そのような考えの母親でしたが、シューマンのピアノの師フリードリヒ・ヴィークの助言もあって、息子が音楽の道に進むことに同意しました。
旅行からライプツィヒに戻ったシューマンは、ヴィーク家に住み込みつつピアノに打ち込みます。ライプツィヒ歌劇場の指揮者ハインリヒ・ドルンからも音楽理論を学びました。
しかしシューマンは、師匠のヴィークの指導に不満を抱いていました。厳格で気難しい性格の師に、イライラが募っていったのでしょう。
ヴィークが演奏旅行に出たのを機に、師匠の家を出てしまいます。ピアノのレッスンは受け続けましたが...
ところがです...
1831年(天保2年)、シューマンは右手にケガを負います。指を鍛えるために自作した器具で練習をしたことが、ケガにつながってしまいました。さらには、目の病気も罹ってしまうのでした。
それだけ音楽(ピアノ)に対して、真摯でストイックな向き合い方をしていたんだね。
シューマンとは、結婚、音楽家として
 ドイツ【ライプツィヒ中央駅】
ドイツ【ライプツィヒ中央駅】1832年(天保3年)、シューマンは作曲家としての道を歩む決断をします。作曲対象としたのは、おもにピアノ曲でした。
1833年(天保4年)、シューマンの兄夫妻が他界します。孤独と恐怖に襲われて気落ちするシューマン。
そのような彼を慰め、励ましたのは、友人ルートヴィヒ・シュンケとパトロンだったフォイクト夫妻でした。
1834年(天保5年)になるとシューマンは恋に落ちます。相手は、師匠ヴィークの弟子として彼女と同居するようになったエルネスティーネ・フォン・フリッケンでした。
婚約までしたシューマンとエルネスティーネでしたが、その後婚約は解消されてしまいます。
その後まもなく、シューマンは師匠の娘クララと恋仲になります。出会った当時は幼かったクララでしたが、1835年(天保6年)には恋愛対象となる年齢になっていたのです。
二人の恋愛に反対だったのがシューマンにとっては師匠であり、クララにとっては父親だったヴィークでした。
ヴィーグからさまざまな妨害を受けたクララは、シューマンとの別れを決意します。しかし、シューマンは引き下がりません。
1837年(天保8年)、シューマンはライプツィヒのリサイタルで、クララに「ピアノソナタ第1番」を献呈したのです。クララは「ピアノソナタ第1番」を演奏しシューマンの気持ちに応えます。その後、手紙でシューマンとの結婚を承諾したのでした。
ヴィークの妨害はその後も続いたため、1839年(天保10年)に訴訟手続きに踏み切ることに。翌1840年(天保11年)、結婚を許可する判決を受けた二人はライプツィヒ近郊の街シェーネフェルトの教会で式を挙げたのでした。
1840年(天保11年)の春から結婚式の直前までの期間は、シューマンが歌曲の作曲に力を入れた時期でした。シューマンがその生涯で作曲した歌曲の大半が、この年に制作されたのです。
シューマンとクララの間には、8人の子供が生まれています。シューマンの収入だけでは不十分だったため、クララも子育てと演奏活動を両立させる必要がありました。
1842年(天保13年)、シューマンは過労で倒れてしまいます。作曲しても思ったような収入に結びつかず、経済的な不安を抱え込んでいたのでしょう。ボヘミアで療養することになりました。
その一方で、ライプツィヒでは音楽的熱量が高まっていました。
1843年(天保14年)、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の常任指揮者だったメンデルスゾーンが、ライプツィヒ音楽院を創設したのです。
そしてシューマンは、ライプツィヒ音楽院で作曲とピアノを教えることになりました。
1844年(天保15年・弘化元年)、シューマンはクララとともにロシアに約5ヶ月間滞在しています。これも負担になったのでしょう。ライプツィヒに戻ったシューマンは、体調悪化に伴い死の恐怖に襲われ始めます。
そのため、ライプツィヒ音楽院での教授の仕事ができなくなってしまいました。幻聴やさまざまな恐怖に襲われていたシューマンは、作曲活動もできなくなってしまったのです。
シューマンとは、ドレスデン時代
 ドイツ・ドレスデン
ドイツ・ドレスデン1844年(天保15年・弘化元年)12月、シューマンはライプツィヒ音楽院の教授の職を辞し、ドレスデンへと移ります。
1845年(弘化2年)には作曲活動も再開できるようになりました。とはいえ、体調が完全に回復したわけではなく、幻聴や双極性障害といった症状に悩まされました。
その後ドイツでは三月革命が起こり、シューマン家族はクライシャに避難しています。
1850年(嘉永3年)、デュッセルドルフの音楽監督のポストを得たシューマンは家族とともに転居を決意します。
シューマンとは、デュッセルドルフ時代とエンデニヒでの最期
 ドイツ・デュッセルドルフ
ドイツ・デュッセルドルフデュッセルドルフで指揮者として参加した最初の演奏会は成功したものの、シューマンの内向的で自閉的な傾向などが影響したためか、楽団員への指導力不足が取り沙汰されるようになっていきます。
病状悪化により指揮することがままならなくなってしまったシューマン。
1854年(嘉永7年・安政元年)には精神病院への入院を促されます。そしてライン川に身投げしたのでした。
幸いなことに救助されたシューマンでしたが、ボン近郊のエンデニヒにある療養所に入ることになりました。
約2年間、家族と離れていたロベルト・シューマンは、1856年(安政3年)7月29日に亡くなりました。
シューマンの作品

ここではシューマンの作品の一部をご紹介します。
| 1832年~1835年 (天保3年~天保6年) |
ピアノソナタ第1番 |
|---|---|
| 1834年~1835年 (天保5年~天保6年) |
ピアノ曲集「謝肉祭」 |
| 1837年~1838年 (天保8年~天保9年) |
ピアノ曲「子供の情景」 ※「トロイメライ」を含む。 |
| 1840年 (天保11年) |
歌曲集「詩人の恋」 |
| 1841年 (天保12年) |
交響曲第1番「春」 |
| 1845年 (弘化2年) |
ピアノ協奏曲 イ短調 |
| 1850年 (嘉永3年) |
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 ※チェロ協奏曲をシューマン自身が編曲。 |
| 1850年 (嘉永3年) |
交響曲第3番「ライン」 |
| 1851年 (嘉永4年) |
ヴァイオリンソナタ第1番 |
まとめ
- シューマンは、19世紀ドイツ・ロマン派を代表する音楽家のひとり。
- 人気作品に「トロイメライ」「ピアノ協奏曲 ニ短調」などがある。
- シューマンといえば、歌曲やピアノ曲が有名。