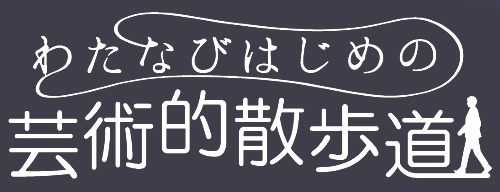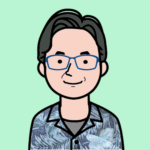ペーテル・パウル・ルーベンスが最晩年に描いた「自画像」は、気品の中に年老いて疲れたような雰囲気を感じる作品です。
老いたとはいえ、宮廷人としての風格を身に纏(まと)った人となりは、自画像からしっかりとにじみ出ています。
2004年(平成16年)、東京都美術館で開催された「ウィーン美術史美術館所蔵 栄光のオランダ・フランドル絵画展」の図録をもとに想いを巡らせてみました。
ペーテル・パウル・ルーベンス作「自画像」とは

- 制作年:1638年~1640年頃
- サイズ:109.5 × 85.0cm
- 油彩、カンヴァス
この作品は、ルーベンスが亡くなる少し前に描いた自画像です。
黒い帽子をかぶり、黒いマントを纏(まと)い、腰に剣を下げた姿は、いかにも騎士といった感じです。
事実ルーベンスは、スペイン国王フェリペ4世とイギリス国王チャールズ1世によりナイトの爵位を授けられていました。
スペイン領南ネーデルラント(フランドル)総督の宮廷画家でもあり、外交官でもあったルーベンス。この「自画像」は、ルーベンスの華々しい経歴を感じさせます。
しかし、さすがに元気な感じには見えません。肌が露出している左手の甲は、シワはなく、血色も良さそうなのですが、表情には少し老いと陰りを感じます。
何よりも目に力を感じません。目の周囲はくぼみ、瞼(まぶた)は重く、キリッとした印象を受けません。
老いを感じるのはそれくらいでしょうか。それ以外の要素からは老いは感じません。
頬は紅潮してして、唇も血色がいいですし、髪や髭からは優雅さを感じます。落ち着いた表情からは威圧感は発せられず、温和な印象を受けます。
ちなみに「ウィーン美術史美術館所蔵 栄光のオランダ・フランドル絵画展」の図録解説によると、ルーベンスは痛風に悩まされていたようです。
おそらくは、ルーベンスが60歳~62歳のときに制作されたこの「自画像」。
勝手な推測ですが、もしかするとこの「自画像」を制作していた時期のルーベンスは、実際にはもっと老け込んでいたのかもしれません。
現代なら60歳といっても若々しい方は沢山いらっしゃいますが、日本でいえば江戸時代前半のころの60歳はもっと老けていたのではないかと思うのです。
西洋と日本では食事も違いますから、ルーベンスは老いてもシャキッとしていたのかもしれませんが…。
痛風を患っていたことから考えるても、豪華な食生活を送っていたのかもしれませんよね。
とはいえ、現代の画像加工ではありませんが、違和感のない程度に若さをプラスして描いたというのが現実なのではないでしょうか。
この「自画像」は、後世の人々に観られても恥ずかしくない、立派な印象を与える魅力的な作品だと思います。
ペーテル・パウル・ルーベンスとは

ペーテル・パウル・ルーベンスは、16世紀~17世紀のフランドル・バロック絵画の巨匠です。
生まれはヴェストファーレン(現在のドイツ)のジーゲンですが、アントウェルペン(アントワープ)で活躍しました。
16世紀~17世紀に活躍したフランドル・バロック絵画の巨匠ルーベンスについては『すぐわかる!フランドル・バロック絵画の巨匠ルーベンスとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ペーテル・パウル・ルーベンス「自画像」について
 ベルギー・アントワープ
ベルギー・アントワープインターネットで1623年(元和9年)に制作されたルーベンスの別の「自画像」(オーストラリア国立美術館所蔵)を観ました。
眼光が鋭く、雰囲気に厳しさを感じ、感情的には冷たい人柄のような印象を受けました。
それに比べて今回ご紹介している「自画像」は、こちら側を睨(にら)みつけるという感じはなく、どことなく目尻に優しさを感じます。
ルーベンス最晩年の「自画像」を観る限り、カッコいい齢の取り方をされたのだ思いました。
最後に、いつものわたなび流の感想で終わりたいと思います。
ペーテル・パウル・ルーベンス作「自画像」は、「美術館で鑑賞したい作品」です。
巨匠ルーベンスの他の作品とともに鑑賞したいですね。
まとめ
- 今回の作品は、ルーベンスの生涯の最後の2年間に描かれた自画像。
- 表情に少し疲れや老いを感じる。
- 威圧感を感じない自然な雰囲気が漂う作品。