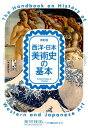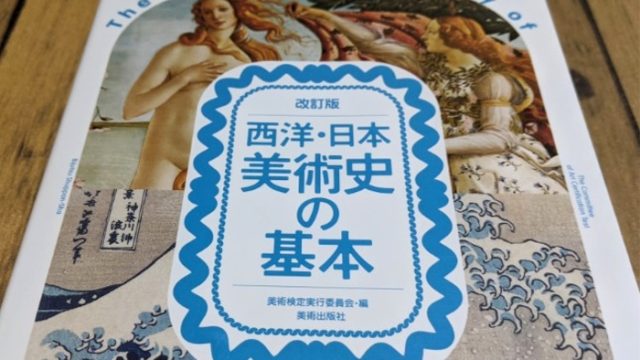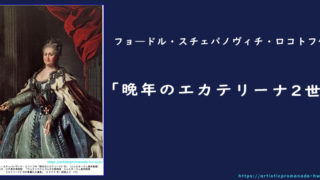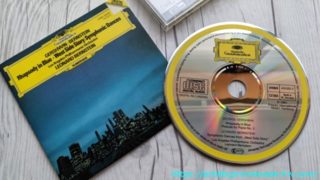美術検定2級合格のための学習を通じて学んだことをご紹介するシリーズ。
恥ずかしながら、2020年3月26日には美術検定の学習意欲低下を吐露してしまいましたが、決意を新たに学習を進めることにしました。
今回からは中世美術編に入ります。初回は「ビザンティンの美術」です。
美術検定の公式テキスト「改訂版 西洋・日本美術史の基本」では、2ページ弱のボリュームです。
- 初期キリスト教の美術
- ビザンティンの美術
この記事でご紹介している画像は、私のセレクト・ミスなどにより本物の画像ではない可能性がありますのでご了承ください。
あらかじめご了承ください。
ビザンティンの美術・概要
美術検定の公式テキストには、中世美術つについて次のような記述があります。
キリスト教への信仰を建築物や祈祷書に込めた時代。
建築を中心に花開いた文化はルネサンスへの予兆でした。出典:『西洋・日本美術史の基本改訂版』美術検定実行委員会 56ページ
美術検定公式テキストでいうところの「中世美術」は、2世紀~15世紀くらいの美術について論じています。
さらには、「初期キリスト教の美術」とは、イエス・キリストが亡くなってから約300年間の美術を指しているようです。すなわち、ローマ帝国がキリスト教を公認するまでの間ですね。
その後は「ビザンティンの美術」へとつながっていきます。
初期キリスト教の美術
ローマ帝国がキリスト教を公認するまでの期間、キリスト教徒はローマ側からの迫害を受けていました。そのためキリスト教徒は、目立たないように活動していました。
迫害者からの目を逃れるため、ローマのキリスト教徒はカタコンベという地下墓地にキリスト教の教えを象徴する壁画を描いていました。
カタコンベの天井によく描かれたのが、羊を肩に乗せた青年(ヘルメス)でした。青年ヘルメスはイエス・キリストを、羊はキリスト教徒を象徴的に表しています。この象徴は、イエス・キリストが「良き羊飼い」を例に教えを説いたことに由来しています。
初期キリスト教の美術作品は、それほど多くは残っていないようです。ローマからの迫害を受けながら信仰を守り通そうとした人々ですから、華美な装飾品や美術品を制作するどころではなかったのかもしれませんね。
4世紀頃にローマで造られたサンティ・ピエトロ・エ・マルチェリーノのカタコンベの壁画なども、芸術家の手による作品という感じがしません。一般の人が描いた印象を受けます。
美しい表現を目指すというよりも、キリストの教えを象徴的に描くことを重視していました。
ビザンティンの美術
紀元330年、ローマ皇帝コンスタンティヌスは首都をビザンティウム(現在のイスタンブール)に遷都し、コンスタンティノープルと改称ます。コンスタンティノープルはその後、東ローマ帝国(ビザンティン帝国)の首都ととなります。
コンスタンティヌス帝は、複数の皇帝によって分割統治されていたローマ帝国を再統一した人物です。ローマ帝国再統一前の西方正帝であった紀元313年には、リキニウス(東方正帝)とともに「ミラノ勅令」を発布し、キリスト教を公認します。また、ローマ皇帝として初めてキリスト教に改宗した人物でもあります。
コンスタンティノープル遷都により、美術にも変化が生じます。東方文化を吸収していたヘレニズム文化やササン朝ペルシアなどの影響が初期キリスト教美術に加わります。
ビザンティンの美術には、大きく2つの「黄金時代」が到来します。
ビザンティン美術・第一次黄金時代
紀元6世紀頃、ユスティニアヌス帝の時代に、壮麗な大聖堂やモザイク画、イコン(聖人などの画像)などが作られます。
第一次黄金時代を代表する作品(建造物を含む)をご紹介します。
- 善き牧者【モザイク画】440年頃 ガッラ・プラチディア廟堂
- ユスティニアヌス帝と廷臣たち【モザイク画】547年 サン・ヴィターレ聖堂
- アヤ(ハギア)・ソフィア大聖堂
ビザンティン美術・第二次黄金時代
紀元8世紀頃になると聖像論争により、聖像の存在を否定する風潮が強まります。紀元726年に、宗教的な絵画や像を偶像崇拝の対象として禁じる勅令が出されたことが発端でした。
その影響でイコノクラスム(聖像破壊運動)が起こり、美術的な視点からみると造形美術は後退します。
しかし、帝国の領土拡大とともにヘレニズム文化への回帰が進み、再び美術的な復興を果たします。それが「第二次黄金期」と呼ばれています。
建造物の規模については、第一次黄金期ほど大きくはなかったようです。
第二次黄金時代を代表する作品名をご紹介します。
- キリストの磔刑【モザイク画】11世紀頃 ダフニ修道院聖堂
- 湾曲した玉座の聖母子【木製パネル・テンペラ】13世紀後半 ワシントン・ナショナル・ギャラリー アンドリュー・メロン・コレクション
ビザンティン美術は中世ヨーロッパ美術に大きな影響を与えることになります。
ビザンティンの美術・作品紹介
ここからは、ビザンティンの美術を画像とともに紹介します。
ビザンティンの美術・善き牧者(ガッラ・プラチディア廟堂)
この「善き牧者」は、イタリア・ラヴェンナのガッラ・プラチディア廟堂にあるモザイクです。紀元440年頃に作られています。
作品に奥行きはそれほど感じられません。その理由としては、宗教的な約束事を重視していることが考えられます。
このような羊飼いと羊をモチーフにした作品は、初期キリスト教の美術によくみられるものです。
イエス・キリストは次のように教えています。
わたしはよい羊飼であって、わたしの羊を知り、わたしの羊はまた、わたしを知っている。それはちょうど、父がわたしを知っておられ、わたしが父を知っているのと同じである。そして、わたしは羊のために命を捨てるのである。
出典:『新約聖書 ヨハネによる福音書 第10章14~15節』
156ページ 日本聖書協会
このようなイエス・キリストの教えをモザイクとして表現したのでしょう。
ビザンティンの美術・サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂
サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂が建っているのはイタリア・ローマ。その名前には「偉大な聖母マリアに捧げられし聖堂」という意味があります。
サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂は、紀元432~440年に建てられました。その建設地には、かつて古代キュベレ神の神殿があったそうです。
これまでに複数の改修が行なわれていますが、ローマのバシリカ(長方形型の平面構造の公会堂)様式で建てられた聖堂としては原構造を残している唯一の建物です。
ビザンティンの美術・アヤ(ハギア)・ソフィア大聖堂

アヤ(ハギア)・ソフィア大聖堂は、現在のトルコ・イスタンブールにある建造物です。東ローマ帝国・ユスティニアヌス帝の時代、紀元532~537年に建てられました。
それ以前にもキリスト教の聖堂が建っていたようですが、2度焼失しています。「ユスティニアヌス帝の時代に再建された」という方が正確なのかもしれません。
「ハギア・ソフィア」とは、ギリシア語で「聖なる叡智」の意味です。
1453年(享徳2年)にトルコに占領された後には、イスラム教の寺院となりました。アヤ(ハギア)・ソフィア大聖堂の周囲に建つ4つの尖塔は、イスラム教の寺院となってから造られています。
アヤ(ハギア)・ソフィア大聖堂を建てた建築家は、次の2人です。
- トラレスのアンテミオス
- ミレトスのイシドロス
まとめ
- ローマ帝国におけるキリスト教公認と、コンスタンティノープル遷都によりビザンティン美術が形成されていった。
- モザイクや建築を中心に発展した。
■参考文献
- 「改訂版 西洋美術の歴史」監修 横山勝彦、半田滋男/編集 美術検定実行委員会/発行 美術出版社
- 「西洋美術の歴史」著者 H・W・ジャンソン、アンソニー・F・ジャンソン/訳者 木村重信、藤田治彦/発行 創元社
■関連書籍のご案内です。
↓