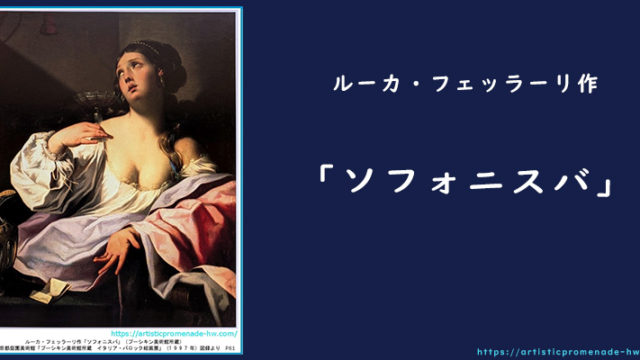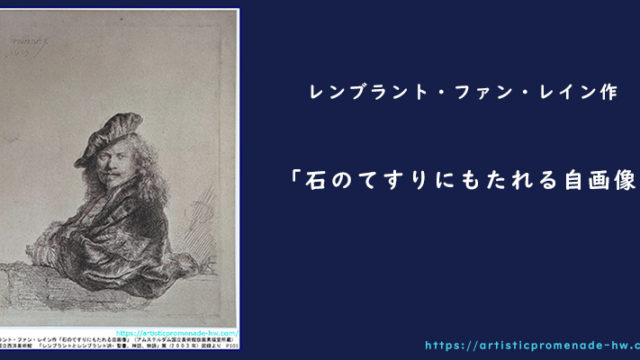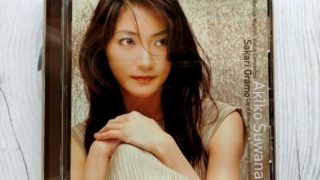いつか行きたい憧れの街ロンドン。
ロンドンといえば…
- ロイヤル・アルバートホールがありBBCプロムスが開催されている。
- レッド・ツェッペリンが使用したスタジオがある。
- MUSEがライブを行なったウェンブリー・スタジアムがある。
- ロミオとジュリエット等で有名なロイヤル・バレエ団がある。
- ターナーの実家あるコヴェント・ガーデンには、1946年以降ロイヤル・バレエ団の本拠地となるロイヤル・オペラハウスがある。
etc...
といった感じです。
とにかく、ロンドンには魅力がいっぱいなのです。
ターナーはそんなロンドンの約200年前の風景を描いていました。
でも、ちょっと違和感が…?
今回は、1997年に横浜美術館にて開催された「テート・ギャラリー所蔵 ターナー展」の図録から、ターナー作「ロンドン」をもとにイマジネーションを膨らませてみようと思います。
ターナー作「ロンドン」とは

- 出品年:1809年
- サイズ:90.2 × 120.0cm
- 油彩、キャンヴァス
ターナーはイギリス・ロンドン出身の画家です。
しかしロンドンを描いた油彩画(完成品)は、今回ご紹介している作品一点のみ。
ですから、この「ロンドン」という作品には、ターナーの強い想いが反映されていると思いたいところです。
まず、作品を眺めてみましょう。
画面上半分を占める空には、晴れ間は見えますが雲がかかっている状態です。雲に反射する太陽光が非常に美しく描かれています。
 セント・ポール大聖堂
セント・ポール大聖堂画面中央の白い雲とともに霞がかって見えるのがロンドンです。遠近法で描かれていて、遠くの街(ロンドン)が大気の効果でハッキリと視認できません。雲の隙間から光が差し込んでいて、明るい蒸気にでも包み込まれているような感じがします。
ロンドン市街地にそびえている塔は、セント・ポール大聖堂だと思われます。
あれッと!ビック・ベンがない?
この作品は1809年(文化6年)の作品です。ビック・ベンができるのは1850年代ですから、それ前の風景だということになります。
タイトルが「ロンドン」なので、ロンドンをメインに扱うと思いきや、遠くに霞んで見える程度にしか描かれていません。
画面中央から少し左に見えるのがテムズ川です。小岩(東京都江戸川区)~市川(千葉県)間の江戸川のように蛇行しているのがわかります。
この作品を観たときに、初めのうちはテムズ川だと気付きませんでした。私の眼には砂漠の砂が舞っているように映ったのです。でもテムズ川です。
 イギリス・旧王立海軍大学
イギリス・旧王立海軍大学テムズ川から視線を中央に戻すと、2つの塔が見えます。これは、旧王立海軍大学です。
 グリニッジ公園
グリニッジ公園画面手前に広がっているのはグリニッジ公園です。
鹿らしき動物も描かれています。日本の奈良や宮島が連想されますね。
 グリニッジ天文台
グリニッジ天文台おそらくターナーは、グリニッジ天文台を背にしながらこの作品を描いています。
ターナーが、自身の故郷ロンドンに対してどのような感情を抱いていたのかはわかりません。
しかし、自分の手で故郷を描けるというのはステキなことだと思います。
普段何気なく通っていた道や、目にしていた風景が恋しくなったんだよね。
ターナーとは
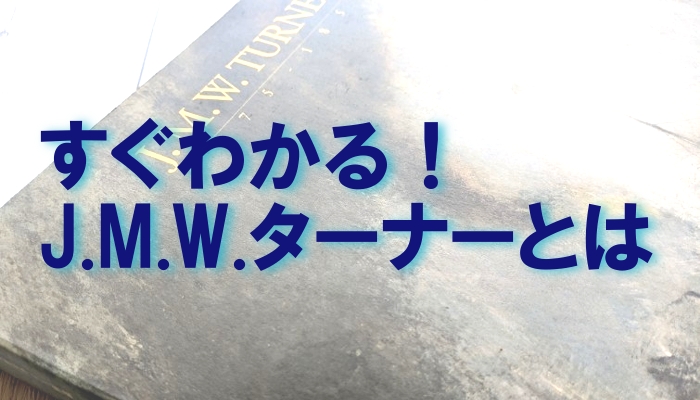
J.M.W.ターナーについては『すぐわかる!J.M.W.ターナーとは』をご参照ください。
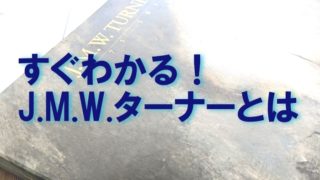
わたなびはじめの感想:ターナー作「ロンドン」について

正直なところ、タイトルが「ロンドン」なのだから、ロンドンの市街地を描いたらよかったのに… と感じないわけではありません。(これが私の感じた違和感の正体です。)
もしも自分が故郷「函館」をテーマに描くとしたら、どこをどのように描くだろうかと妄想してみました。
私が通っていた高校は、函館山の麓(ふもと)の八幡坂を登りきったところに建っています。

観光で来られた方が、八幡坂から見下ろす景色を撮影している姿をよく見ました。坂の先には函館港があり、写真映えする景色のひとつです。(その背後の建物が高校です。)
麓といってもそれなりに坂道を登るので、在学中には「坂の下に建てて欲しかった」と思っていました。ところが卒業してしまうと考えは180度変わり、「やっぱりあそこでなければダメだね」となりました。
話を絵に戻しますね。
上述の八幡坂の景色も描きたいが、他にも候補はあります。

八幡坂からでもある程度は見えますが、高校のグラウンド辺りから見る「函館の夕景」も捨てがたいです。グラウンドは校舎よりもさらに上にありましたので、十分函館の街並みを見下ろすことができました。
ちなみに上図は函館山からの景色です。

もうひとつは5月くらいの五稜郭公園でしょうか。桜でピンクに染まる時期です。
子供の頃には五稜郭公園でよく遊んでいました。親戚の家が近かったことと、小学校に上がる前に住んでいたのが五稜郭の側だったことが関係しています。
函館の市電も絵になりますね。特に雪が降っている景色は最高です。
このようにいろいろと考えてみましたが、私には「函館が遠くに見える景色」を描こうという発想には至りませんでした。
函館の遠景を描くとしたら、次の2つになると思います。
- 船で沖に出る。
- 青函トンネルを抜けて北海道に入ったあと海を挟んで見えてくる景色。
書きながら、ひとつ思い出したことがあります。
私は帰省する際に、寝台列車をよく利用していました。理由は、「飛行機よりも天候に左右されにくいだろう」と思っていたからです。
北斗星も利用しました。
上野から青森まで寝台列車を利用し、その後は海峡(たぶん急行)に乗り換えることもありました。
3段の寝台列車のときもありましたね。3段の場合、一番下がスペースが広く、窓も大きかったのでお気に入りでした。
上野から乗る際には、進行方向の右側の指定席を購入することにしていました。
その理由は上述の②に関係しています。北海道に入った後、窓から海越しに函館を眺めながら列車の旅を楽しめたからです。
あるとき、函館の街に霧がかかっていことがありました。思い出したこととはこの景色のことです。それは、函館山が陸地と切り離されて、海にぽつんと浮かんでいるような幻想的な光景でした。
その景色がターナーの「ロンドン」と重なることに気が付きました。「遠く霞んでいる故郷」という部分がです。
このように考えると、ターナーの意図とは違うかもしれませんが「ロンドン」という作品にロマンチックさを感じます。
もしかするとターナーは、遠近法を活用して描くことに重きを置いていただけなのかもしれませんが、私の個人的な経験を重ねて解釈してみました。
最後にいつものごとく、わたなび流の感想で終わります。
ターナー作「ロンドン」は、「美術館や西洋風の部屋などで鑑賞したい(欲しいとまでは思わない)作品」です。
多分、僕の知っている景色とはだいぶ違っていると思うけれど…
まとめ
- ターナーはロンドン出身の画家。
- ロンドンと題する作品に描かれているターナーの故郷は遠く霞んでいる。
- ターナーが描いた「ロンドン」は、グリニッジ公園からの景色だと思われる。