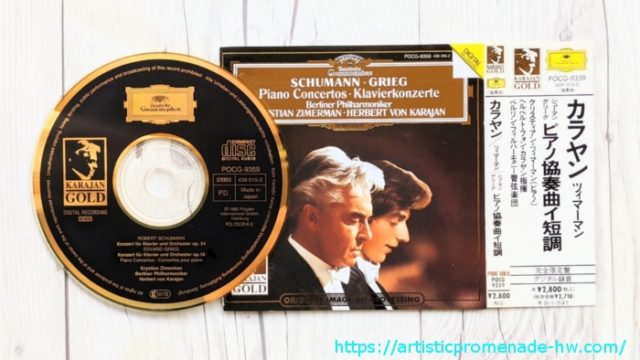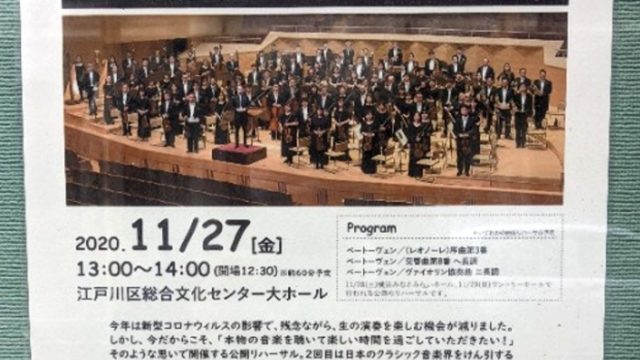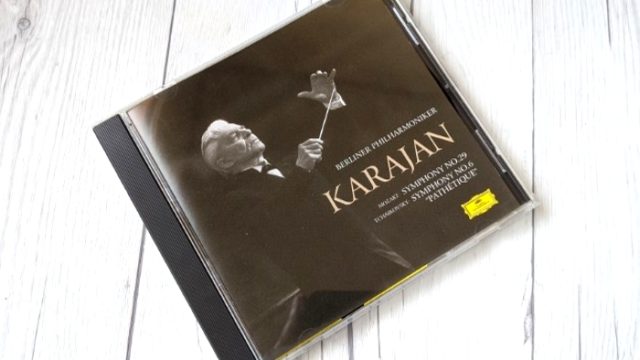交響曲第9番≪新世界より≫で有名な作曲家ドヴォルザーク。
アントニン・レオポルト・ドヴォルザークとはどのような作曲家だったのでしょうか?
その生涯についてわかりやすくご紹介します。
ドヴォルザークとは
 チェコの町並み【市庁舎広場】
チェコの町並み【市庁舎広場】アントニン・レオポルト・ドヴォルザークは、チェコ出身でロマン派の作曲家です。
ドヴォルザークは、オーストリア帝国ネラホゼヴェスで1841年(天保12年)9月8日に誕生しました。
ドヴォルザークの家族は、宿屋と肉屋を営んでいました。ドヴォルザークの父親は、ツィターと呼ばれるオーストリアやスイスで用いられる弦楽器が上手だったようです。
若き日のドヴォルザークの音楽教育
 チェコ・プラハ
チェコ・プラハドヴォルザークが音楽を学び始めたのは、小学校に入った6歳頃からです。小学校の校長がヴァイオリンの指導をしたところ、見る間に上達したそうです。
しかし、ドヴォルザークは小学校を中退することになります。父親が肉屋を継がせるために、30kmほども離れた町に修行に行かせるためでした。
ところが幸いなことに、ドヴォルザークはその町の職業訓練校の校長アントニン・リーマンと出会います。この人物は音楽に精通していました。
ドヴォルザークは肉屋の技術修得書取得のためにドイツ語を学ぶことがが必須であり、そのドイツ語を教えていたのがアントニン・リーマンだったのです。
結局ドヴォルザークはリーマン校長から、器楽演奏(ヴァイオリン、オルガン、ヴィオラ)や和声学をといった音楽理論における基礎を学ぶことができました。
1857年(安政4年)になると、ドヴォルザークはプラハにあるオルガン学校へ入学します。しかし、家計は厳しい状況であったため、費用は伯父が援助してくれました。この学校は2年間で卒業します。
彼の才能を伸ばしてあげたかったんだろうね。
卒業後、レストランなどで演奏をしていたドヴォルザークでしたが、チャンスが到来します。
ドヴォルザーク、スメタナとの出会い~作曲家へ
 チェコ・プラハ旧市街
チェコ・プラハ旧市街1862年(文久2年)、チェコの人々によって国民劇場の建設が決定。その完成までの期間、仮劇場のオーケストラでヴィオラ奏者になることができたのです。
そして1866年(慶応2年)、このオーケストラにスメタナが指揮者として着任したのです。スメタナといえば、連作交響詩「わが祖国」で有名ですよね。(この当時は「わが祖国」作曲前ですが…)
ドヴォルザークはスメタナの指導を受けることができたのです。その後ドボルザークは作曲に専念するため、1871年(明治4年)にオーケストラを辞めます。
1874年(明治7年)には、プラハにある聖ヴォイチェフ教会(聖アダルベルト教会)のオルガニストの職を得ます。このことはドボルザークの経済的な安定につながりました。
同年ドヴォルザークは、交響曲第3番、第4番などをオーストリア政府が拠出する国家奨学金を得るための審査に提出します。翌1875年(明治8年)には奨学金を受けられることになり、毎年の審査を経て5年間奨学金を受け続けました。
1878年(明治11年)からは、ブラームスとの交流も始まります。
1884年(明治17年)、ドヴォルザークはイギリスのロイヤル・アルバート・ホールで指揮をする機会を得ます。その際演奏した、自身作曲の宗教作品「スターバト・マーテル」は大歓声を受けます。
1888年(明治21年)にプラハを訪れたドヴォルザークは、チャイコフスキーと親しくなります。
ドヴォルザークの受賞歴
この時期のドヴォルザークは様々な賞や栄誉を受けています。
- オーストリア三等鉄王冠賞【1889年】
- チェコ科学芸術アカデミー会員に推挙【1890年】
- プラハ音楽院教授就任【1890年】
- プラハ大学名誉博士号授与【1891年】
- ケンブリッジ大学名誉音楽博士号授与【1891年】
その後、ドヴォルザークに転機が訪れます。
ドヴォルザークの転機、いざアメリカへ~交響曲第9番≪新世界より≫の誕生
 アメリカ合衆国・ニューヨーク
アメリカ合衆国・ニューヨーク1891年(明治24年)、ニューヨーク・ナショナル音楽院の音楽院院長としてアメリカに招かれたのです。当初はそれほど前向きではなかったようですが、結局引き受けることになります。
その際の年俸は、プラハ音楽院時代の約25倍だというのですから、ものすごい好待遇だといえます。そのような環境で交響曲第9番「新世界より」が作曲されました。
しかし世界は大恐慌の危機にさらされます。ドヴォルザークの報酬にも影響が及び、支払いの遅れ状況が続くことに…
1895年(明治28年)、ドヴォルザークはアメリカを離れ帰国します。
故郷へ戻ったドヴォルザークとその晩年
 ドヴォルザーク像
ドヴォルザーク像帰国したドヴォルザークは、プラハ音楽院での教職に戻り、作曲活動も継続します。同1895年には、ウィーン楽友協会から名誉会員に推挙されます。
これまでオペラのヒット作が無かったドヴォルザークでしたが、この分野でも成功を収め始めます。しかし、ウィーンで上演されなかったこともあり、オペラで世界的な名声を得ることはできませんでした。最後のオペラ作品は不評で終わってしまいます。
1901年(明治33年)、ドヴォルザークはプラハ音楽院院長に就任します。
持病(尿毒症、動脈硬化症)のあったドヴォルザークでしたが、1904年(明治37年)にそれが再発してしいます。その後休むも意識を失い、ドヴォルザークは同年5月1日に亡くなりました。死因は脳出血でした。
ドヴォルザークの代表作

ここではドヴォルザークの作品を一部ご紹介します。
| 協奏曲 | ピアノ協奏曲【作曲:1876年】 |
|---|---|
| ピアノ連弾曲・ 管弦楽曲 |
スラヴ舞曲 第1集【作曲:1878年/管弦楽版も同年。】 |
| 協奏曲 | ヴァイオリン協奏曲【作曲:1879年】 |
| 室内楽曲 | ピアノ五重奏曲 第2番【作曲:1887年】 |
| 管弦楽曲 | 交響曲第9番≪新世界より≫【作曲:1893年】 |
| 弦楽四重奏曲 | 弦楽四重奏曲 第12番≪アメリカ≫【作曲:1893年】 |
| 協奏曲 | チェロ協奏曲【作曲:1894年~1895年】 |
| 管弦楽曲 | 交響詩「水の精」【作曲:1896年】 |
| 管弦楽曲 | 交響詩「野ばと」【作曲:1896年】 |
| 管弦楽曲 | 交響詩「英雄の歌」【作曲:1897年】 |
まとめ
- ドヴォルザークはチェコ出身でロマン派の作曲家。
- 父親は肉屋を継がせたかった。
- オーケストラのヴィオラ奏者時代には指揮者スメタナから指導を受けた。
- ドヴォルザークの最大の代表作は交響曲第9番≪新世界より≫。