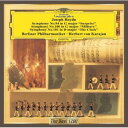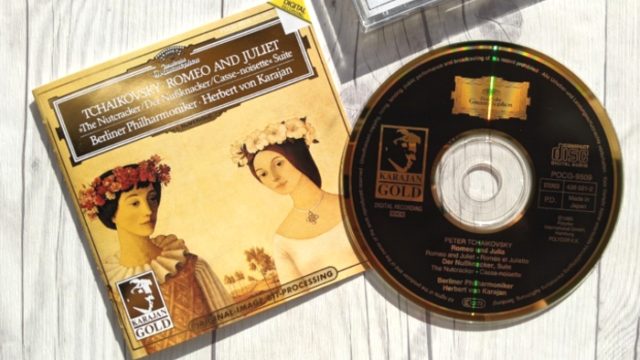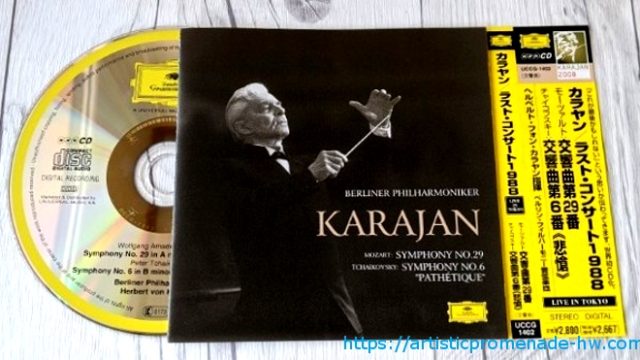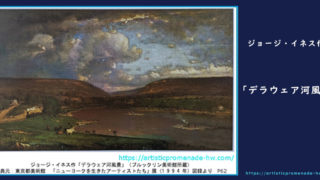オーストリア出身の古典派を代表する作曲家のひとりであるフランツ・ヨーゼフ・ハイドンは、どのような生涯を送ったのでしょうか?
ハイドンと言えば、「交響曲の父」「弦楽四重奏曲の父」などと呼ばれる音楽家です。
わかりやすくご紹介します。
ハイドンとは
 オーストリア・ウィーン
オーストリア・ウィーンフランツ・ヨーゼフ・ハイドンが生まれたのは、1732年(享保17年)3月31日です。場所は神聖ローマ帝国・下オーストリア大公国ニーダーエスターライヒ州ローラウ村でした。
ハイドンの家業は車大工で、暮らしはそれほど裕福ではなかったようです。両親は音楽好きでした。
5歳の頃、義理の叔父(父親の妹の配偶者)であり、音楽学校の校長でもあったマティアス・フランクに音楽的才能を見出され、音楽を学び始めます。残念ながら、満足できるような指導は受けられませんでした。
1740年(元文5年)、シュテファン大聖堂のゲオルク・フォン・ロイターに才能を認められウィーンに移り住み、聖歌隊の一員になります。音楽の都ウィーンで音楽を生業にできたことは、ハイドンにとっては幸せなことだったと思います。
しかしハイドンに転機が訪れます。変声期で声が変わってしまったのです。
1749年(寛延2年)、9年間勤めた聖歌隊を解雇されてしまいます。その後の数年間は、安定した仕事に就くことはできなかったようです。10代後半のハイドンにとっては試練の時期でした。
その頃のハイドンは、ヴァイオリンやオルガンの演奏、教会の歌手などをして生計を立てていました。うれしい出来事としては、次の2人のイタリア人に出会えたことです。
- ピエトロ・メタスタージオ:詩人・オペラの台本作家
- ニコラ・ポルポラ:イタリア後期バロックの作曲家
ポルポラについては、従者をしていた時期がありました。
この頃からハイドンは、本格的に作曲を勉強しはじめます。ポルポラの影響も受けたのではないでしょうか。
ハイドンは、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ(J・S・バッハの息子の一人で作曲家)の影響を強く受けたようです。
1750年(寛延3年)頃には「ミサ・ブレヴィス ヘ長調」を作曲します。これは現存するハイドン最初期の作品です。
1750年代後半、ハイドンはカール・モルツィン伯爵の宮廷楽長に就任します。この時期にハイドンは、交響曲第1番をはじめとして交響曲だけでも約15曲を作曲しています。
ハイドンがモルツィン伯爵に仕えた期間は不明ですが、経済的な問題により解雇の憂き目にあいます。
その後、1761年(宝暦11年)には、エステルハージ家で副楽長の職に就いています。エステルハージ家は西部ハンガリーの名門貴族でした。
この副学長時代にも、ハイドンは約25曲の交響曲を作曲しています。
1766年(明和3年)、前楽長が亡くなり、ハイドンが楽長に昇進します。ハイドンの仕事は多岐に渡り、作曲だけでなくオペラ歌手との契約などもこなしていました。
1780年(安永9年)頃には、エステルハージ家におけるハイドンの評価も高くなっていたようです。ハイドンはエステルハージ家に約30年間仕えるなかで、すばらしい楽曲の提供だけでなく、真面目に仕事に取り組んでいたのだと思います。
1781年(安永10年・天明元年)頃にはモーツァルトとの出会いがあります。
ハイドンとモーツァルトの年齢差は24歳、大人と子供ほどの違いがありますが、二人は互いを尊敬し合っていました。どちらかというと「友人」という関係性だったようです。この出会いからモーツァルトが亡くなるまでの約10年間、親交は続きました。
1790年(寛政2年)のエステルハージ家・宮廷楽団の解散に伴い、ハイドンはフリーの作曲家として歩みはじめます。
 ロンドン・ビッグベン&テムズ川
ロンドン・ビッグベン&テムズ川同年、ハイドンはイギリス・ロンドンで演奏会の機会を得ます。イギリス訪問は2回行なわれ、公演は大成功!
ハイドンはこのイギリス訪問の際に作曲も行なっています。
- 交響曲第 94番「驚愕」
- 交響曲第100番「軍隊」
- 交響曲第103番「太鼓連打」
- 交響曲第104番「ロンドン」
etc...
ハイドンの名声は広がり、経済的にも成功しました。
イギリスの市民権取得も考えたようですが、ハイドンはウィーンに戻ります。
1802年(享和2年)には、持病の悪化で作曲が困難になります。
フランツ・ヨーゼフ・ハイドンは、1809年(文化6年)5月31日にオーストリア・ウィーンで亡くなりました。葬儀には大勢の参列者が訪れました。
なびさんぽで紹介しているハイドン作品
 オーストリア・ウィーン【シェーンブルン宮殿】
オーストリア・ウィーン【シェーンブルン宮殿】【なびさんぽ】でご紹介しているハイドンの作品は次の通りです。
| 交響曲 | 交響曲第94番「驚愕」 |
|---|---|
| 交響曲 | 交響曲第101番「時計」 |
まとめ
- ハイドンは音楽好きの両親のもとに生まれた。
- 宮廷音楽家からフリーの作曲家へ。
- ロンドンでの公演が大成功!
■関連CDのご案内です。
↓