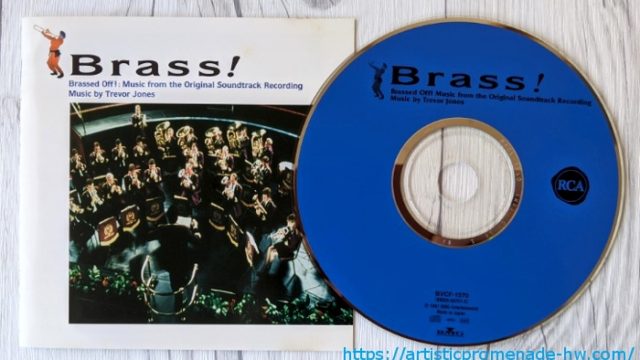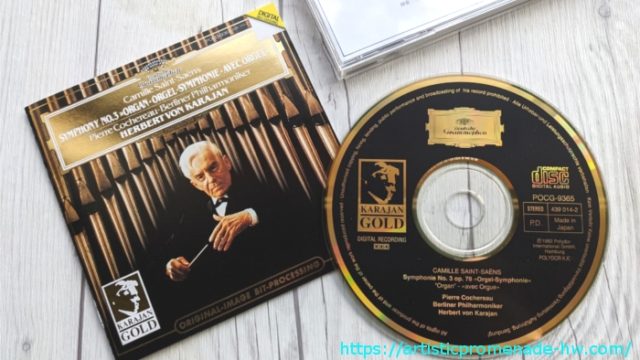J・S・バッハが作曲をした「コラール:いと尊きイエスよ、われらはここに集いて BWV731」は、短いですがとても美しいの楽曲です。
『トッカータとフーガ ニ短調 鈴木雅明/バッハ・オルガン名曲集』【CD】で聴いた感想をご紹介します。
■トッカータとフーガ ニ短調 鈴木雅明/バッハ・オルガン名曲集
- オルガン:鈴木雅明
アンゲルミュンデのマリア教会(ドイツ) - ROMANESCA【KICC 193】
- 発売元:キングレコード株式会社
J・S・バッハ「コラール:いと尊きイエスよ、われらはここに集いて BWV731」とは
 パイプオルガン・イメージ
パイプオルガン・イメージ「コラール:いと尊きイエスよ、われらはここに集いて BWV731」についての知識を、私はほとんど持ち合わせていません。制作時期も不明です。
そこで、【CD】『トッカータとフーガ ニ短調 鈴木雅明/バッハ・オルガン名曲集』のライナーノーツから「コラール:いと尊きイエスよ、われらはここに集いて BWV731」の解説の一部をご紹介しましょう。
このコラールは、説教の前に歌われるべきものとしてクラウスニッツァーが書いたものだが、バッハはこのコラールの編曲を7曲も残している。
出典:『トッカータとフーガ ニ短調 鈴木雅明/バッハ・オルガン名曲集 ライナーノーツ』
鈴木雅明著 6ページ
解説からわかることは、次の3点です。
- 「コラール:いと尊きイエスよ、われらはここに集いて BWV731」は、説教前に歌うことを主目的として作られた楽曲である。
- 同コラールを書いたのが、クラウスニッツァーという人物であったということ。
- バッハは同コラールを7曲分も編曲している。
クラウスニッツァーの詞に、バッハが曲を付けたわけではなくて。
「編曲」とあることから、クラウスニッツァーは曲を作ったという理解でよさそうですね。(すでに書いたことそのままですが...)
歌詞はもしかすると、新約聖書から引用されているのかもしれません。(推測の域を出ませんが...)
バッハの手にかかれば、1つの素材が何パターンにもアレンジされてしまうということなのでしょう。
ここでひとつ疑問が...
「コラール:いと尊きイエスよ、われらはここに集いて BWV731」の作曲者がクラウスニッツァーなら、なぜバッハの曲として扱われているのでしょう?
オリジナルを超えるほどの編曲ということなのでしょうか...
それとも、作曲者は違うけれどバッハが編曲したのだから、あえて明記しなくてもバッハの曲として扱おうということなのかもしれませんね。
J・S・バッハとは
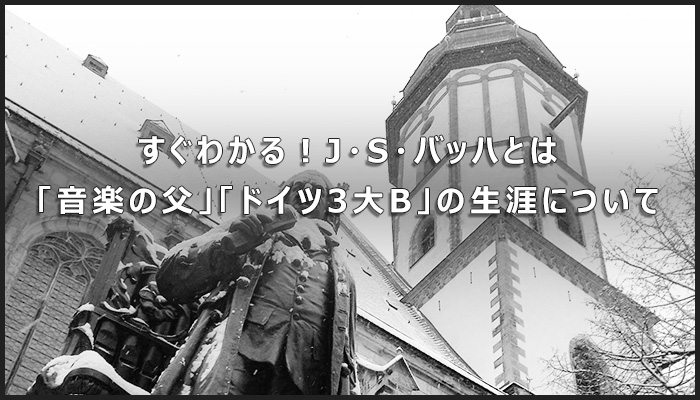
18世紀にドイツで活躍した音楽家ヨハン・セバスティアン・バッハ(J・S・バッハ)については、『すぐわかる!J・S・バッハとは|「音楽の父」「ドイツ3大B」の生涯について』をご参照ください。
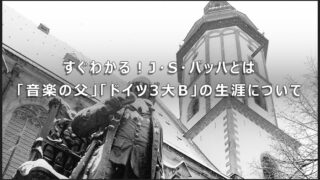
わたびはじめの感想:J・S・バッハ「コラール:いと尊きイエスよ、われらはここに集いて BWV731」について

ここからは『トッカータとフーガ ニ短調 鈴木雅明/バッハ・オルガン名曲集』に収録されている、J・S・バッハ作曲「コラール:いと尊きイエスよ、われらはここに集いて BWV731」の感想をお伝えします。
※【 】は、今回聴いたCDでの演奏時間です。
■「コラール:いと尊きイエスよ、われらはここに集いて BWV731」【2分27秒】
第1音から癒しムードいっぱいです。ゆったりと曲が進行していきます。穏やかで、安らぎを感じます。
高音(ソプラノ?)のコラールの旋律がハッキリと聴こえてきますが、低音がやさしく手を添えるように支えている感じが伝わってきます。
冒頭部分の「タラリ~」は「トッカータとフーガ ニ短調 BWV565」をちょっぴり連想させますが、音色が笛を吹いているようなやさしい感触なので全く別物に聴こえます。
これもリラックスにピッタリの楽曲ではないでしょうか。
「リラックスにピッタリ」などと書いてしまいましたが、この作品は説教が始まる前に歌うことを主な目的として作られた楽曲でしたね。
おそらく心を落ち着かせた状態で、説教に集中できるように作られたのではないかと思います。曲名からも、「イエス様、私たちはここに集まりました」と、説教を聞く準備ができている信者の方々の気持ちが想像できますよね。
「コラール:いと尊きイエスよ、われらはここに集いて BWV731」は短いですが、とても美しい楽曲です。
でも...気持ち良くなって、眠ってしまうかもしれないな。

まとめ
- 「コラール:いと尊きイエスよ、われらはここに集いて BWV731」はクラウスニッツァーが書き、バッハが編曲した。
- 説教の前に歌うのが主な目的だった楽曲。
- 制作年などは不明。
■関連CDのご案内です。
↓