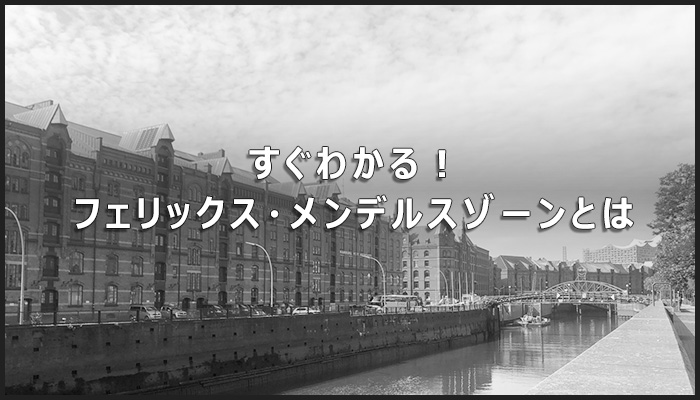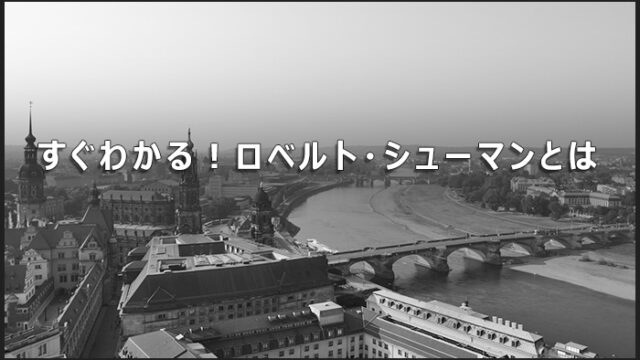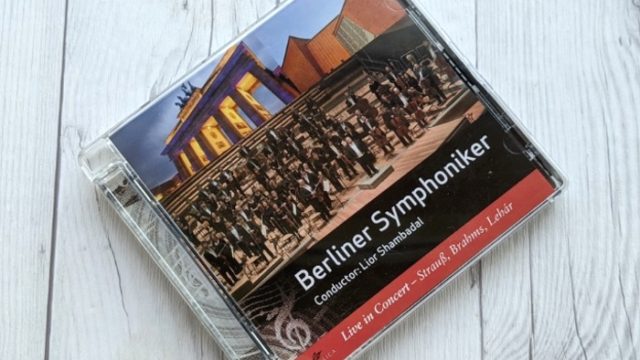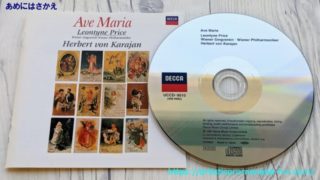メンデルスゾーンはドイツ・ロマン派の作曲家です。
「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」や演奏会用序曲「フィンガルの洞窟」をはじめ、多くの名曲を作曲しました。
作曲家としてだけでなく指揮者やピアニスト、オルガニストとしても活躍したメンデルスゾーン。音楽においてマルチな才能を発揮した人物です。
ここではメンデルスゾーンの生涯を、わかりやすくご紹介します。
フェリックス・メンデルスゾーンの誕生と音楽教育
 ドイツ・ハンブルク
ドイツ・ハンブルクフェリックス・メンデルスゾーンは、1809年(文化6年)2月3日にドイツのハンブルクで誕生しました。
本来の名前はもっと長く、カタカナ表記で「ヤーコプ・ルートヴィヒ・フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ」です。
父親が銀行家であったこともあり、メンデルスゾーンは裕福な家庭で育ちました。母親からはピアノを学んでいます。
幼い頃のメンデルスゾーンは神童として評判でした。
フェリックス・メンデルスゾーンの両親は、息子の才能を伸ばすことに熱心だったようです。父親が仕事でパリへ赴任する際には同行させ、ピアノ教師であるマリー・ビゴーからレッスンを受けさせていました。(本人の希望だったのかもしれませんが…)
1817年(文化14年)、フェリックス・メンデルスゾーンはベルリンにおいて、作曲家で音楽教師でもあったカール・フリードリヒ・ツェルターから作曲を学びはじめました。
フェリックス・メンデルスゾーン、指揮者として
 ドイツ・ライプツィヒ【トーマス教会 バッハ像】
ドイツ・ライプツィヒ【トーマス教会 バッハ像】1829年(文政12年)メンデルスゾーンが20歳のとき、自らの監督・指揮でバッハの「マタイ受難曲」を公開演奏しています。ベルリン・ジングアカデミーで開催されたこの公演の大成功。追加公演も行なわれるほどでした。
1829年(文政12年)は、メンデルスゾーンが初めてイギリスを訪問した年でもありました。メンデルスゾーンは生涯に10回(計約20か月間)イギリスに滞在しています。ヴィクトリア女王との謁見の機会もありました。
1835年(天保6年)には、ドイツ・ライプツィヒに本拠地を置くライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者に就任します。
1841年(天保12年)には、ベルリンの宮廷礼拝堂楽長に就任します。プロイセン国王のフリードリヒ・ヴィルヘルム4世がメンデルスゾーンを招きました。
フェリックス・メンデルスゾーンの晩年、教育者として
 ドイツ【ライプツィヒ中央駅】
ドイツ【ライプツィヒ中央駅】メンデルスゾーンは音楽家の指導・養成にも力を注いでいたようです。
1843年(天保14年)にはメンデルスゾーン自身が資金調達のために動き、ライプツィヒ音楽院を開校しました。院長はメンデルスゾーン、ピアノと作曲の教授には当時33歳のロベルト・シューマンが招かれました。
しかしメンデルスゾーンに悲しい出来事が起こります。姉であるファニーが亡くなったのです。
1847年(弘化4年)、姉の訃報を聞いたメンデルスゾーンは神経障害を患います。一時は回復傾向にあったようですが、数ヶ月には意識を失い、翌日11月4日に亡くなりました。
ライプツィヒのゲヴァントハウス前には、メンデルスゾーンの記念碑が建てられました。
メンデルスゾーンの代表曲
 Andre Loh-KlieschによるPixabayからの画像:メンデルスゾーン銅像
Andre Loh-KlieschによるPixabayからの画像:メンデルスゾーン銅像メンデルスゾーンの代表曲を数作品ご紹介します。
| 1826年 (文政9年) |
序曲「夏の夜の夢」 |
|---|---|
| 1829年~1842年 (文政12年~天保13年) |
交響曲第3番「スコットランド」 ※作曲&改訂。 |
| 1830年 (文政13年・天保元年) |
演奏会用序曲「フィンガルの洞窟」 |
| 1833年 (天保4年) |
交響曲第4番「イタリア」 |
| 1843年 (天保14年) |
劇付随音楽「夏の夜の夢」 ※結婚行進曲が含まれています。 |
| 1844年 (天保15年・弘化元年) |
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 |
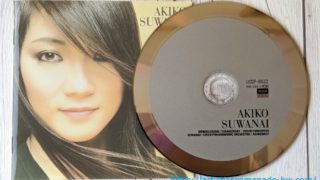
まとめ
- メンデルスゾーンはドイツ・ロマン派の作曲家。
- 指揮者やピアニスト、オルガニストとしても活躍。
- メンデルスゾーンの作曲した「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」は個人的に大好きな作品。