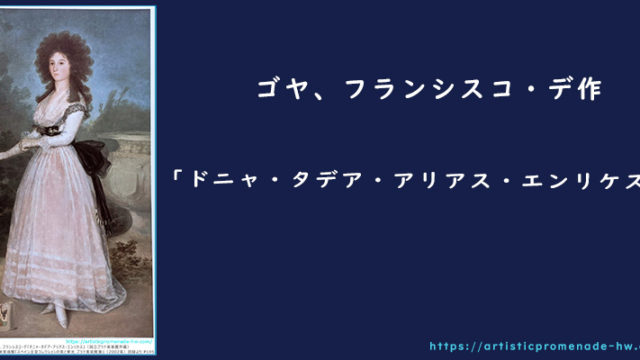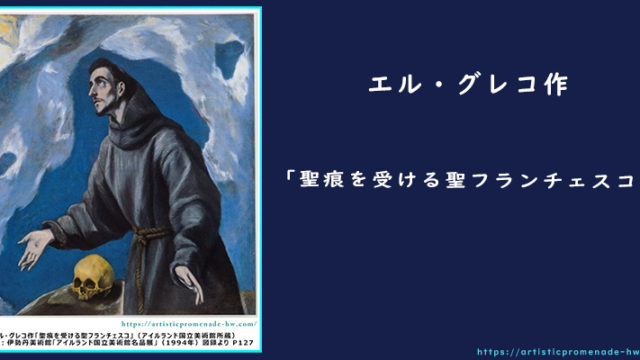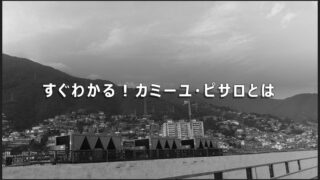19世紀のフランスの画家ウジェーヌ・ドラクロワとは、どのような生涯を送ったのでしょうか?
わかりやすくご紹介します。
ウジェーヌ・ドラクロワとは
 フランス・パリ
フランス・パリフェルディナン・ヴィクトール・ウジェーヌ・ドラクロワは、19世紀のフランスの画家です。ドラクロワは、主観や感受性を重要視したロマン主義を代表する画家のひとりでもありました。
ドラクロワは1798年(寛政10年)4月26日、パリ近郊の街シャラントン=サン=モーリス(現在のサン=モーリス)で誕生しました。
父親(戸籍上)は大臣や知事を務めた人物のようです。母親はルイ16世の宮廷家具師の娘でした。
ドラクロワは10代で両親を失っています。
ドラクロワは17歳で新古典主義の画家ピエール=ナルシス・ゲランの弟子となります。翌年にはパリ美術学校に入学。ドラクロワは、ピーテル・パウル・ルーベンスやパオロ・ヴェロネーゼらからも影響を受けたと言われています。
1822年(文政5年)には、「ダンテの小舟」がサロン(官展)で入賞します。この作品は高い評価を得、政府に買い上げられています。
2年後には「キオス島の虐殺」を出品しましたが、ギリシャ独立戦争で起きた実際の事件を題材としていたこともあり評価の賛否は分かれます。その後「キオス島の虐殺」は、政府が買上げることになりました。
ドワクロワが32歳の頃、フランスで激動が起こります。1830年(文政13年・天保元年)、王政復古で復活したブルボン朝を打倒するべく市民革命が起きたのです。フランス七月革命と呼ばれるこのできごとにより、ルイ・フィリップが王位を得ます。
この栄光の三日間を描いたのが、有名な「民衆を導く自由の女神」です。ドラクロワの躍動的で大胆な色彩感覚が、存分に発揮された作品です。
 モロッコ【シャウエンの旧市街】
モロッコ【シャウエンの旧市街】ドラクロワはフランス政府の記録画家としても活躍していました。1832年(天保3年)、政府より派遣された外交使節とともにモロッコに訪問しています。北アフリカや南スペインも旅しました。
モロッコ訪問時に、ドラクロワはデッサンを残しており、1834年(天保5年)にはそれを基に「アルジェの女たち」を描いています。
ドワクロワは生涯を通じて画家として精力的に活動を続け、リュクサンブール宮やサン・シュルピス聖堂、サン・ドニ・デュ・サン・サクルマン聖堂、パリ市庁舎、ルーブル美術館といった建築物の装飾なども手掛けました。
1855年(安政2年)、33歳のとき、ドラクロワはレジオン・ドヌール勲三等賞を授章します。
1861年(万延2年・文久元年)には美術アカデミーの会員になっています。8回の落選を経験した後のことでした。
1863年(文久3年)8月13日、ドワクロワはフランス・パリのアトリエ兼自宅にて65歳で亡くなりました。
なびさんぽで紹介しているウジェーヌ・ドラクロワ作品
 セーヌ川のイメージ(パリ)。
セーヌ川のイメージ(パリ)。【なびさんぽ】でご紹介しているウジェーヌ・ドラクロワの作品は次の通りです。
| 聖ステファーノの遺体を運び去る弟子達 | 制作年:1860年(安政7年・万延元年)。 【丸沼芸術の森所蔵】 |
|---|
まとめ
- 33歳のときに「レジオン・ドヌール勲章」を授章。
- 1832年(天保3年)、モロッコを訪問。
- 1861年(万延2年・文久元年)には美術アカデミーの会員に。