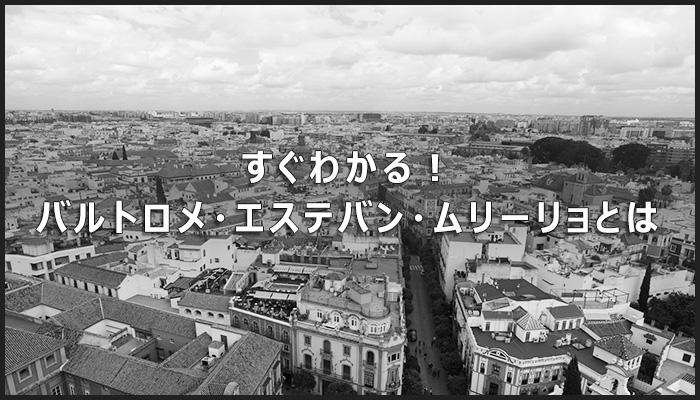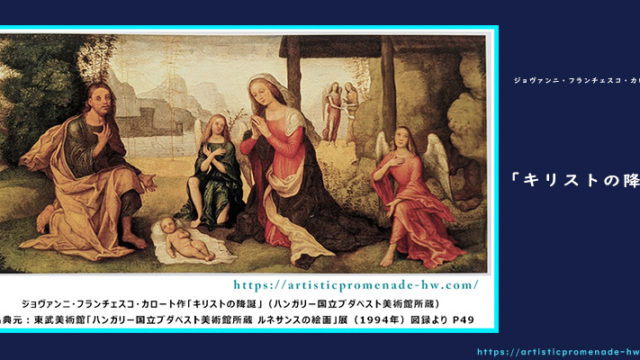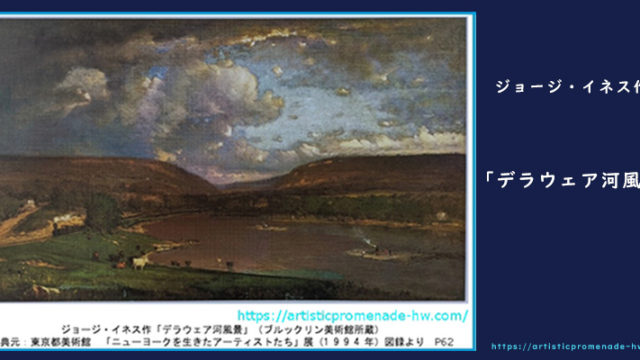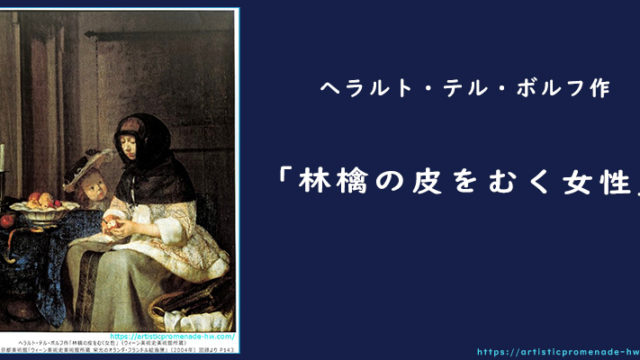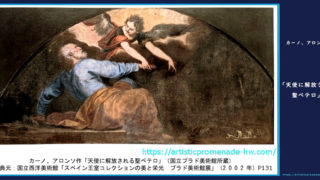バルトロメ・エステバン・ムリーリョは、17世紀のスペイン・バロック期に活躍した画家です。
スペイン黄金時代美術を代表する画家にはムリーリョの他、ディエゴ・ベラスケス、フランシスコ・デ・スルバラン、アロンソ・カーノらがいます。
ムリーリョとは、どのような生涯を送ったのでしょうか?
わかりやすくご紹介します。
ムリーリョとは、誕生~修業時代
 スペイン・セビリアの街並み
スペイン・セビリアの街並みバルトロメ・エステバン・ムリーリョは、1617年(元和3年)12月31日にスペイン・セビリアで誕生しました。14人兄弟の末っ子でした。
でも、少しうらやましいな。
ムリーリョの父親は民間の医者でした。しかし両親は、ムリーリョが若い頃に他界してしまいます。その後のムリーリョの生活状況についての詳細はわかりませんが、結婚していたお姉さんが面倒をみてくれたようです。
ムリーリョが画家として修業していたのは1630年代のこと。この時期はフランシスコ・デ・スルバランの活躍していた時期と重なります。
ムリーリョとは、画家としての活躍 1650年代
 スペイン・セビリアの街並み
スペイン・セビリアの街並み1645年(正保2年)ムリーリョは、セビリアのフランシスコ会修道院から装飾に関する大きな受注を手掛けます。この大規模受注はムリーリョにとっては初めてのことで、彼が頭角を現すキッカケになりました。
当初、デネスプリモ(明暗主義)を主調としていた描いていたムリーリョ。しかし1650年代に入ると、彼の画風は色彩が豊かなものに変わっていきます。
ムリーリョの画風変更に影響を与えたのがフランシスコ・エレーラ(子)でした。エレーラはイタリアの盛期バロック絵画に精通していた人物です。
ムリーリョのセビリアにおける人気は高まり、イタリアやヨーロッパ北部の商人たちに支持されていきます。富裕層を顧客に持ったことで、ムリーリョの生活は経済的な安定を得たはずです。
ムリーリョとは、画家としての活躍 1660年代~晩年
 スペイン・セビリア
スペイン・セビリアバルトロメ・エステバン・ムリーリョの画家としての最盛期は1660年~1670年代のこと。
この時期に、ムリーリョのもとには大規模な依頼が入ります。
- カリダー施療院聖堂の装飾
- サンタ・マリア・ラ・ブランカ聖堂の装飾
etc...
「無原罪の御宿り」に代表されるムリーリョの、幻想的でやわらかく、やさしさを伝える作品は、バロック期のカトリック教会の宗教イメージに合致していたようです。
宗教画だけでなく風俗画も描いたムリーリョの作品は、外国人の顧客の手を通じてヨーロッパ中へと渡っていきました。特にイギリスでの評価が高く、後のイギリス絵画にも影響を与えています。
マドリードに住んだ時期があるとも言われていますが、ムリーリョはその生涯のほとんどをセビリアまたはその周辺地域で過ごしていたと考えられています。
バルトロメ・エステバン・ムリーリョは、1682年(天和2年)4月3日に亡くなりました。カディス(セビリア南方の街)の修道院での作業中に、足場から落ちたことが原因でした。
ムリーリョの作品について
 スペイン・セビリア【黄金の塔】
スペイン・セビリア【黄金の塔】バルトロメ・エステバン・ムリーリョの作品について、おもにプラド美術館が所蔵している絵画を中心に列挙してみます。
| 1645年~1650年 (正保2年~慶安3年) |
「蚤をとる少年」 【ルーブル美術館所蔵】 |
|---|---|
| 1650年~1655年 (慶安3年~承応4年・明暦元年) |
「レベカとエリエゼル」 【プラド美術館所蔵】 |
| 1655年~1660年頃 (承応4年・明暦元年~万治3年)頃 |
「善き羊飼い」 【プラド美術館所蔵】 |
| 1668年 (寛文8年) |
「無原罪の御宿り」 【セビーリャ美術館所蔵】 |
| 1670年~1680年頃 (寛文10年~延宝8年)頃 |
「無原罪の御宿り」 【プラド美術館所蔵】 |
| 不明 | 「ニコラス・オスマール」 【プラド美術館所蔵】 |
まとめ
- ムリーリョは、17世紀のスペイン・バロック期に活躍した画家のひとり。
- 宗教関連の作品を多く手掛けたが、少数ながら風俗画も描いた。
- 「無原罪の御宿り」は有名。